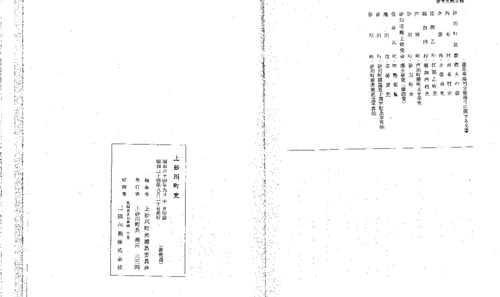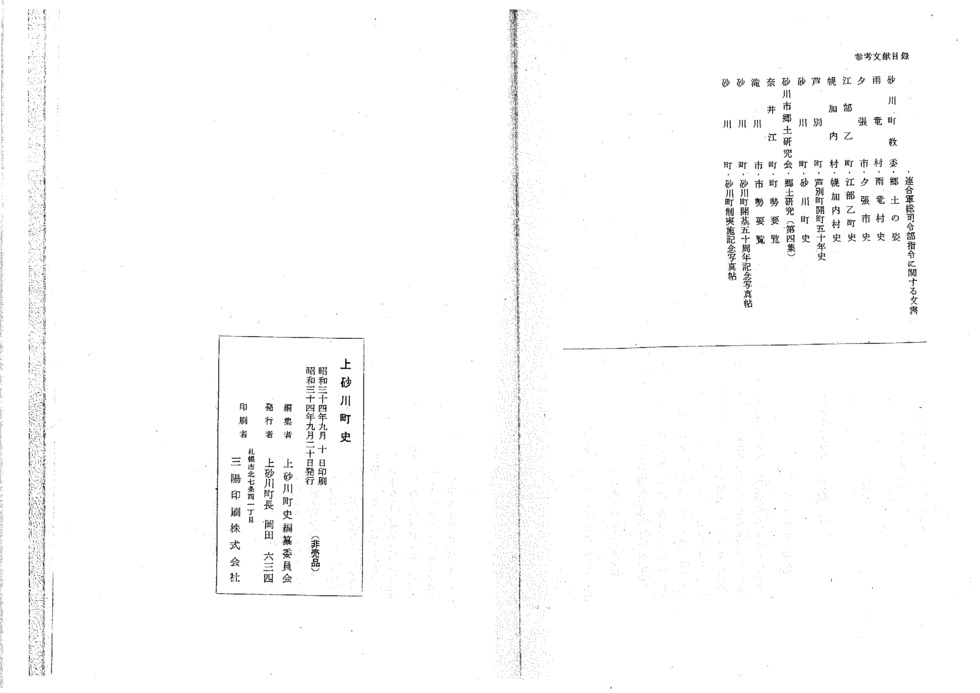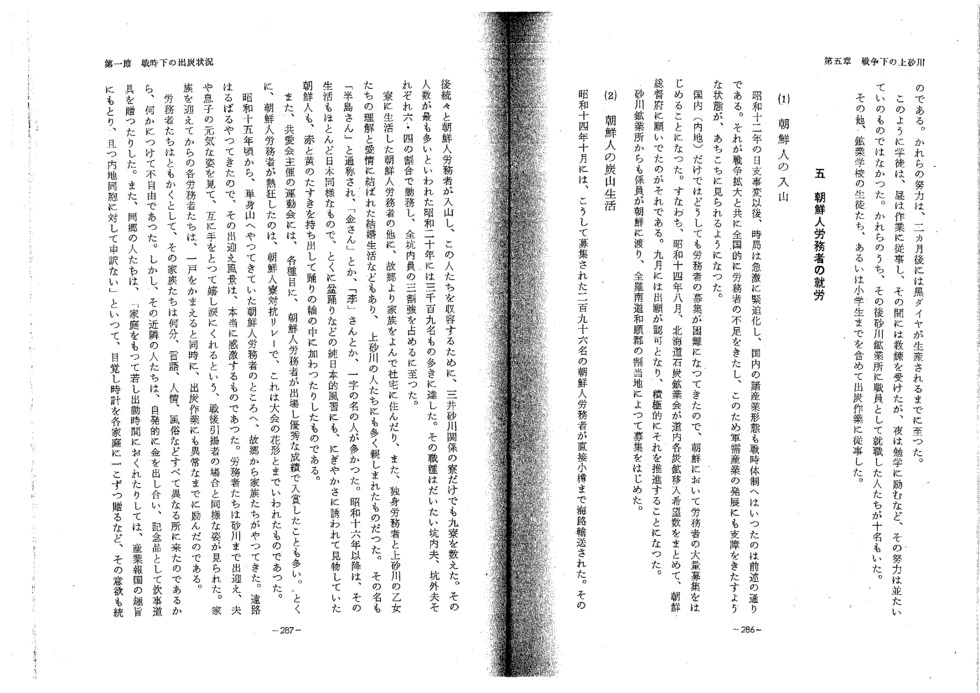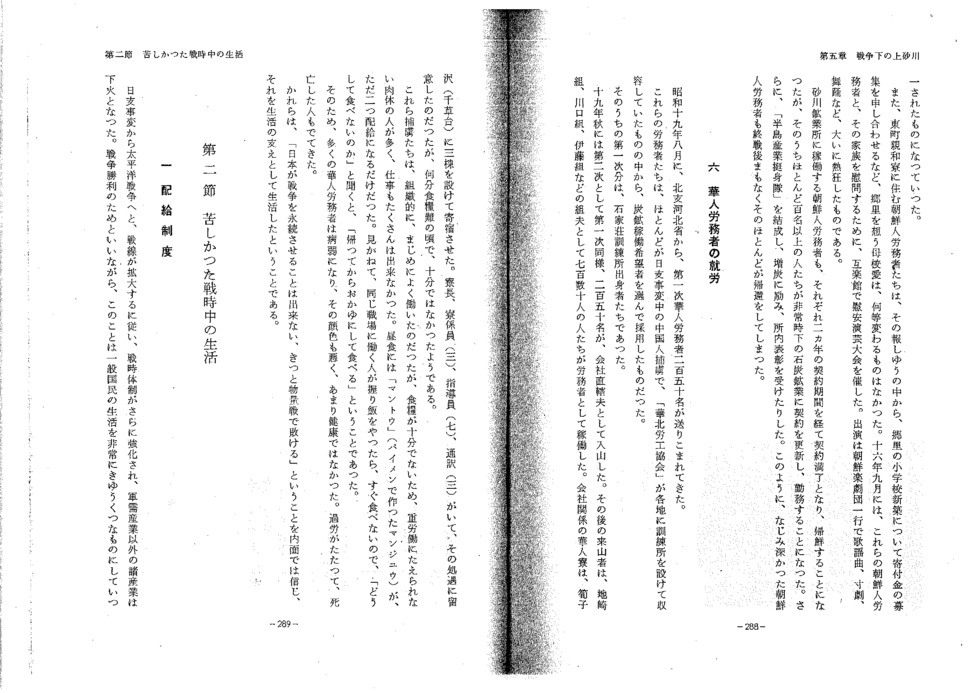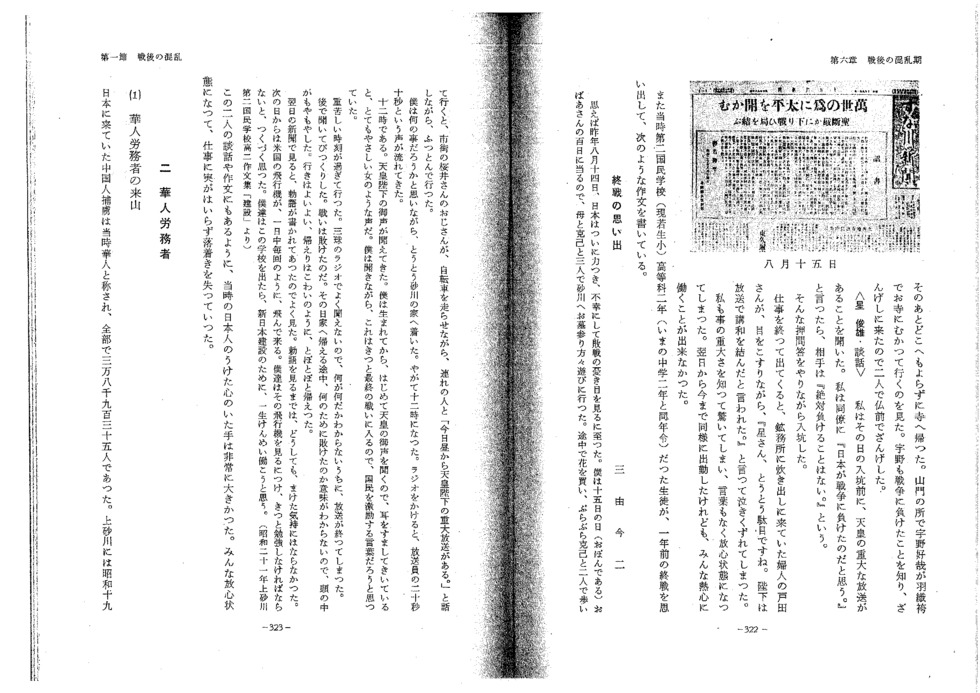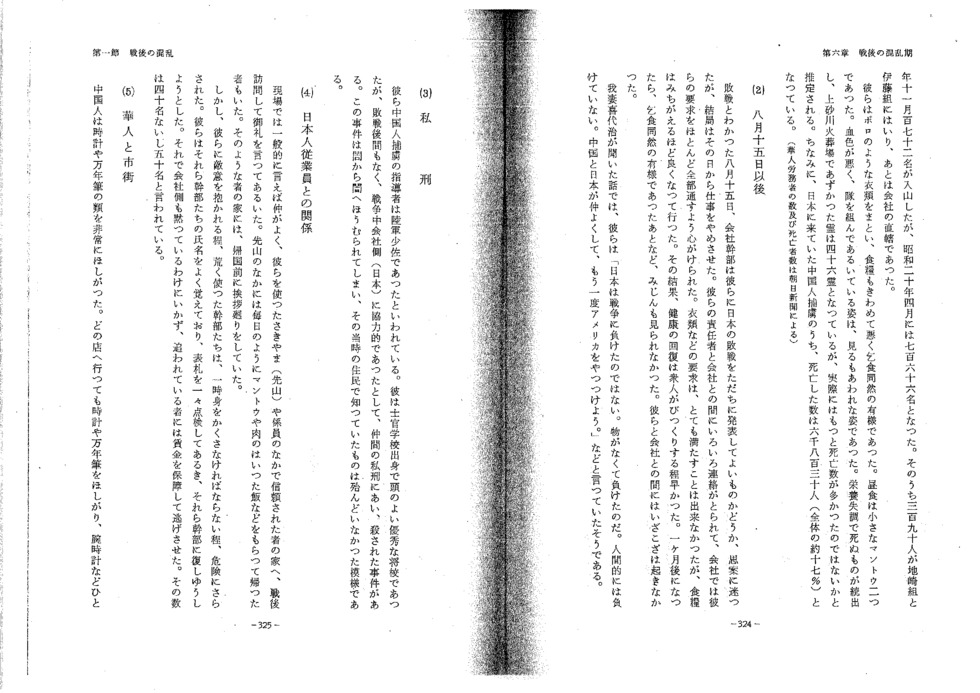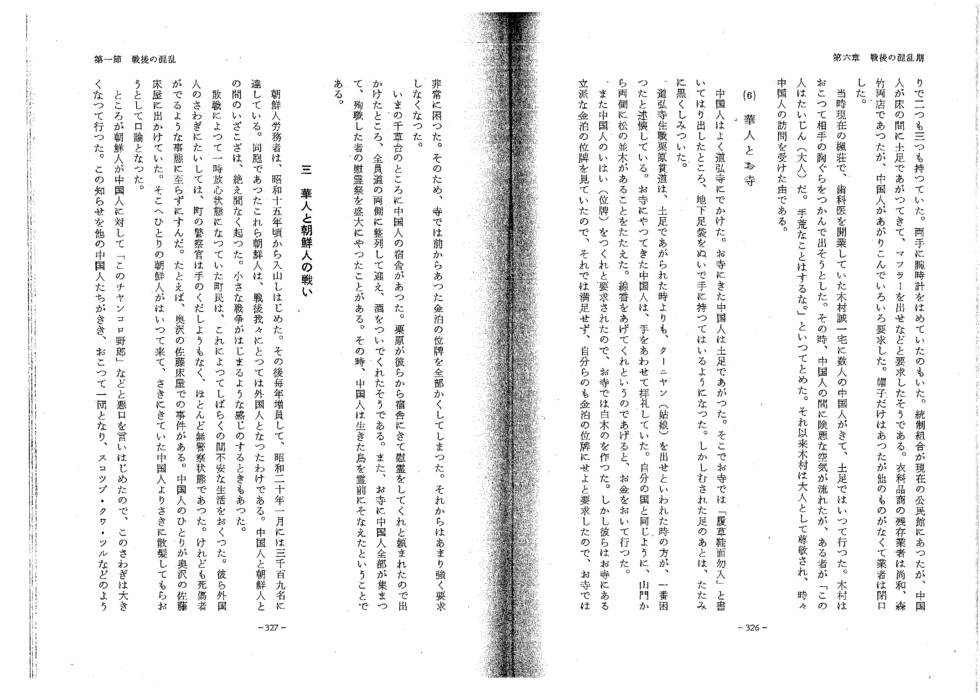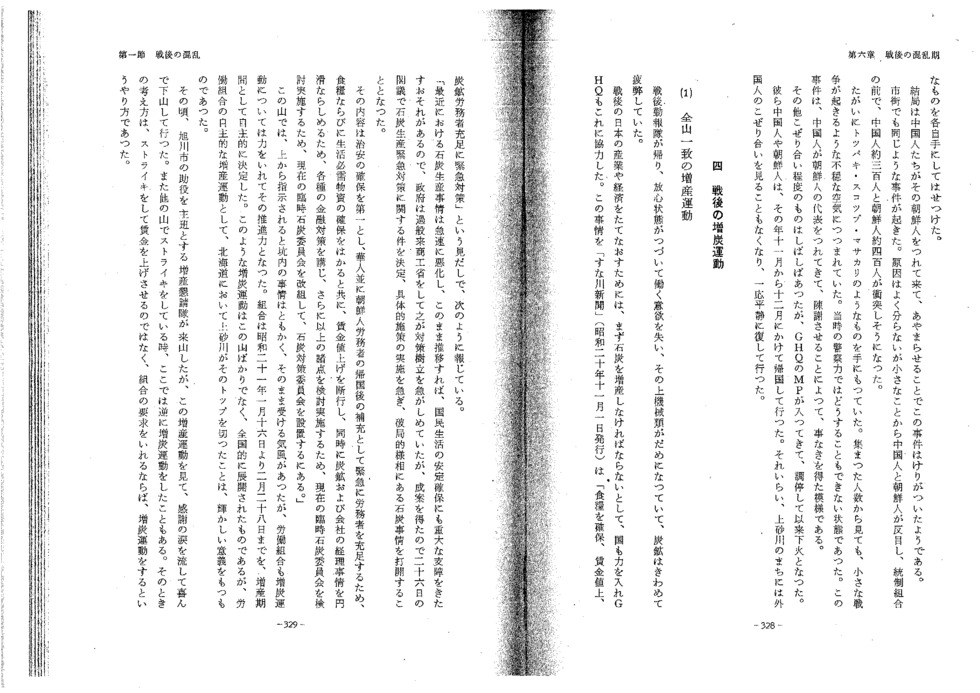上砂川町史
発行年:1959年(昭和34年)9月20日
編集者:上砂川町史編纂委員会
286ページ~289ページ
第一節 第五章 五 朝鮮人労務者の就労~六 華人労務者の就労
323ページ~328ページ
第一節 第六章 二 華人労務者~三 華人と朝鮮人の戦い
上砂川町は北海道空知支庁管内にあり、東部は南北に走る夕張山脈、西部は石狩平野に連なり、三井鉱山の所有する上砂川炭田を擁する炭鉱の町であったが、同炭鉱は昭和62(1987)年7月に閉山した。町史は昭和34(1959)年に編纂されたが、昭和63(1988)年には『新上砂川町史』が編纂されている。
この町史には、戦時中に炭鉱での労働に従事していた朝鮮人、中国人の様子についての記述がある。
- 著作者:
- 上砂川町史編纂委員会
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
p286~289
五 朝鮮人労務者の就労
⑴ 朝鮮人の入山
昭和十二年の日支事変以後、時局は急激に緊迫化し、国内の諸産業形態も戦時休制へはいつたのは前述の通りである。それが戦争拡大と共に全国的に労務者の不足をきたし、このため軍需産業の発展にも支障をきたすような状態が、あちこちに見られるようになつた。
国内(内地)だけではどうしても労務者の募集が困難になつてきたので、朝鮮において労務者の大量募集をはじめることになつた。すなわち、昭和十四年八月、北海道石炭鉱業会が道内各炭鉱移入希望数をまとめて、朝鮮総督府に願いでたのがそれである。九月には出願が認可となり、積極的にそれを推進することになつた。
砂川鉱業所からも係員が朝鮮に渡り、全羅南道和順郡の割当地によつて募集をはじめた。
⑵ 朝鮮人の炭山生活
昭和十四年十月には。こうして募集された二百九十六名の朝鮮人労務者が直接小樽まで海路輸送された。その後続々と朝鮮人労務者が入山し、この人たちを収容するために、三井砂川関係の寮だけでも九寮を数えた。その人数が最も多いといわれた昭和二十年には三千百九名もの多きに達した。その職種はだいたい坑内夫、坑外夫それぞれ六・四の割合で勤務し、全坑内員の三割強を占めるに至つた。
寮に生活した朝鮮人労務者の他に、故郷より家族をよんで社宅に住んだり、また、独身労務者と上砂川の乙女たちの理解と愛情に結ばれた結婚生活などもあり、上砂川の人たちにも多く親しまれたものだつた。その名も「半島さん」と通称され、「金さん」とか、「李」さんとか、一字の名の人が多かつた。昭和十六年以降は、その生活もほとんど日本同様なもので、とくに盆踊りなどの純日本的風習にも、にぎやかさに誘われて見物していた朝鮮人も、赤と黄のたすきを持ち出して踊りの輪の中に加わつたりしたものである。
また、共愛会主催の運動会には、各種に、朝鮮人労務者が出場し優秀な成績で入賞したことも多い。とくに、朝鮮人労務者が熟狂したのは。朝鮮人寮対抗リレーで、これは大会の花形とまでいわれたものであつた。
昭和十五年頃から、単身山へやつてきていた朝鮮人労務者のところへ、故郷から家族たちがやつてきた。遠路はるばるやつてきたので、その出迎え風景は、本当に感激するものであつた。労務者たちは砂川まで出迎え、夫や息子の元気な姿を見て、互に手をとつて嬉し涙にくれるという、戦後引揚者の場合と同様な姿が見られた。家族を迎えてからの各労務者たちは、一戸をかまえると同時に、出炭作業にも異常なまでに励んだのである。
労務者たちはともかくとして。その家族たちは何分、言語、人情、風俗などすべて異なる所に来たのであるから、何かにつけて不自由であつた。しかし、その近隣の人たちは、自発的に金を出し合い、記念品として炊事道具を贈つたりした。また、同郷の人たちは、「家庭をもつて若し出勤時間におくれたりしては、産業報国の趣旨にもとり、且つ内地同胞に対して申訳ない」といつて、目覚し時計を各家庭に一こずつ贈るなど、その意欲も統一されたものになつていつた。
また、東町親和寮に住む朝鮮人労務者たちは、その報しゆうの中から。郷里の小学佼新築について寄付金の募集を申し合わせるなど。郷里を想う母校愛は、何等変わるものはなかつた。十六年九月には、これらの朝鮮人労務者と、その家族を慰問するために、互楽館で慰安演奏大会を催した。出演は朝鮮楽劇団一行で歌謡曲、寸劇、舞踊など、大いに熱狂したものである。
砂川鉱業所に稼働する朝鮮人労務者も、それぞれ二ヵ年の契約期間を経て契約満了となり、帰鮮することになつたが、そのうちほとんど百名以上の人たちが非常時下の石炭鉱業に契約を更斬し、勤務することになつた。さらに、「半鳥産業挺身隊」を結成し、増炭に励み、所内表彰を受けたりした。このように、なじみ深かつた朝鮮人労務者も終峨後まもなくそのほとんどが帰還をしてしまつた。
六 華人労務者の就労
昭和十九年八月に、北支河北省から。第一次華人労務者二百五十名が送りこまれてきた。
これらの労務者たちは、ほとんどが日支事変中の中国人捕虜で、「華北労工協会」が各地に訓練所を設けて収容していたものの中から、炭鉱稼働希望者を選んで採用したものだつた。
そのうちの第一次分は、石家荘訓練所出身者たちであつた。
十九年秋には第二次として第一次同様、二百五十名が、会社直轄夫として入山した。その後の来山者は、地崎組、川口組、伊藤組などの組夫として七百数十人の人たちが労務者として稼働した。会社関保の華人寮は、筍子沢(千草台)に三棟を設けて寄宿させた。寮長、寮係員(三)、指導員(七)、通訳(三)がいて、その処遇に留意したのだつたが、何分食糧難の頃で。十分ではなかつたようである。
これら捕虜たちは、組織的に、まじめによく慟いたのだつたが、食糧が十分でないため、重労動にたえられない肉体の人が多く、仕事もたくさんは出来なかつた。昼食には「マントウ」(パイメンで作つたマンジユウ)が、ただ二つ配給になるだけだつた。見かねて、同じ職場に働く人が握り飯をやつたら、すぐ食ぺないので、「どうして食べないのか」と聞くと、「帰つてからおかゆにして食べる」ということであつた。
そのため、多くの華人労務者は病弱になり、その顔色も悪く、あまり健康ではなかつた。過労がたたつて、死亡した人もでてきた。
かれらは、「日本が戦争を永続させることは出来ない、きつと物量戦で敗ける」ということを内面では信じ、それを生活の支えとして生活したということである。
P322~326
二 華人労務者
⑴ 華人労務者の来山
日本に来ていた中国人捕虜は当時華人と称され、全鄙で三万八千九百三十五人であった。上砂川には昭和十九年十一月百七十二名が入山したが、昭和二十年四月には七百六十六名となつた。そのうち三百九十人が地崎組と伊藤組にはいり、あとは会社の直轄であつた。
彼らはボロのような衣類をまとい、食糧もきわめて悪く乞食同然の有様であつた。昼食は小さなマントウ二つであつた。血色が悪く、隊を組んであるいている姿は、見るもあわれな姿であつた。栄養失調で死ぬものが続出し、上砂川火葬場であずかつた霊は四十六霊となつているが、実際にはもつと死亡数が多かつたのではないかと推定される。ちなみに。日本に来ていた中国人捕虜のうち、死亡した数は六千八百三十人(全休の約十七%)となつている。(華人労働者の数及び死亡者数は毎日新聞による)
⑵ 八月十五日以後
敗戦とわかつた八月十五日、会杜幹部は彼らに日本の敗戦をただちに発表してよいものかどうか、思案に迷つたが、結局はその日から仕事をやめさせた。彼らの責任者と会社との間にいろいろ連絡がとられて、会社では彼らの要求をほとんど全部通すよう心がけられた。衣類などの要求は、とても満たすことは出来なかったが、食糧はみちがえるほど良くなつて行つた。その結果、健康の回復は衆人がびつくりする程早かつた。一ヶ月後になつたら、乞食同然の有様であつたあとなど、みじんも見られなかつた。彼らと会社との間にはいざこざは起きなかつた。
我妻喜代治が聞いた話では、彼らは「日本は戦争に負けたのではない。物がなくて負けたのだ。人間的には負けていない。中国と日本が仲よくして、もう一度アメリカをやつつけよう。」などと言つていたそうである。
⑶ 私刑
彼ら中国人捕虜の指導者は陸軍少佐であつたといわれている。彼は士官学校出身で頭のよい優秀な将校であつたが、敗戦後間もなく、戦争中会社側(日本)に協力的であつたとして、仲間の私刑にあい、殺された事件がある。この事件は闇から闇へほうむられてしまい、その当時の住民で知つていたものは殆んどいなかつた模様である。
⑷ 日本人従業員との関係
現場では一般的に言えぱ仲がよく、彼らを使つたさきやま(先山)や係員のなかで信頼された者の家へ、戦後訪問して御礼を言つてあるいた。先山のなかには毎日のようにマントウや肉のはいつた飯などをもらつて帰つた者もいた。そのような者の家には、帰国前に挨拶廻りをしていた。
しかし、彼らに敵意を抱かれる程、荒く使つた幹部たちは、一時身をかくさなければならない程、危険にさらされた。彼らはそれら幹郡たちの氏名をよく覚えており、表札を一々点検してあるき、それら幹部に復しゆうしようとした。それで会社側も黙つているわけにいかず、追われている者には賃金を保障して逃げさせた。その数は四十名ないし五十名と言われている。
⑸ 華人と市街
中国人は時計や万年筆の類を非常にほしがつた。どの店へ行つても時計や万年筆をほしがり、腕時計などひとりで二つも三つも持つていた。両手に腕時計をはめていたのもいた。統制組合が現在の公民館にあつたが、中国人が床の問に土足であがつてきて、マフラーを出せなどと要求したそうである。衣料品商の残存業者は尚和、森竹両店であつたが、中国人があがりこんでいろいろ要求した。帽子たけはあつたが他のものがなくて業者は閉口した。
当時現在の楓荘で、歯科医を開業していた木村誠一宅に数人の中国人がきて、土足ではいつて行つた。木村はおこつて相手の胸ぐらをつかんで出そうとした。その時、中国人の間に険悪な空気が流れたが、ある者が「この人はたいじん(大人)だ。手荒なことはするな。」といつてとめた。それ以来木村は大人として尊敬され。時々中国人の訪問を受けた由である。
⑹ 華人とお寺
中国人はよく道弘寺にでかけた。お寺にきた中国人は土足であがつた。そこでお寺では「履草鞋而勿人」と書いてはり出したところ、地下足談をぬいで手に持つてはいるようになつた。しかしむされた足のあとは。たたみに黒くしみついた。
道弘寺住職栗原貫道は、土足であがられた時よりも。クーニヤン(姑娘)を出せといわれた時の方が、一番困つたと述懐している。お寺にやつてきた中国人は、手をあわせて拝礼していた。自分の国と同じように、山門から両側に松の並木があることをたたえた。線香をあげてくれというのであげると、お金をおいて行つた。
また中国人のいはい(位牌)をつくれと要求されたので、お寺では白木のを作つた。しかし彼らはお寺にある立派な金泊の位牌を見ていたので、それでは満足せず、自分らのも金泊の位牌にせよと要求したので、お寺では非常に困つた。そのため、寺では前からあつた金泊の位牌を全部かくしてしまつた。それからはあまり強く要求しなくなつた。
いまの千草台のところに中国人の宿舎があつた。栗原が彼らから宿舎にきて慰霊をしてくれと頼まれたので出かけたところ、全員道の両側に整列して迎え、洒をついでくれたそうである。また、お寺に中国人全部が集まつて、殉職した者の慰霊祭を盛大にやつたことがある。その時、中国人は生きた鳥を霊前にそなえたということである。
三 華人と朝鮮人の戦い
朝鮮人労務者は、昭和十五年頃から入山しはじめた。その後毎年増員して、昭和二十年一月には三千百九名に達している。同胞であつたこれら朝鮮人は、戦後我々にとつては外国人となつたわけである。中国人と朝鮮人との間のいざこざは、絶え間なく起つた。小さな戦争がはじまるような感じのするときもあつた。
敗戦によつて一時放心状態になつていた町民は、これによつてしばらくの間不安な生活をおくつた。彼ら外国人のさわぎにたいしては、町の警察官は手のくだしようもなく、ほとんど無警察状態であつた。けれども死傷者がでるような事態に至らずにすんだ。たとえば、奥沢の佐藤床屋での事件がある。中国人のひとりが奥沢の佐藤床屋に出かけていた。そこへひとりの朝鮮人がはいつて来て、さきにきていた中国人よりさきに散髪してもらおうとして口論となつた。
ところが朝鮮人が中国人に対して「このチヤンコロ野郎」などと悪口を言いはじめたので。このさわぎは大きくなつて行つた。この知らせを他の中国人たちがきき、おこつて一団となり、スコツプ・クワ・ツルなどのようなものを各自手にしてはせつけた。
結局は中国人たちがその朝鮮人をつれて来て、あやまらせることでこの事件はけりがついたようである。
市街でも同じよ5な事件が起きた。原因はよく分らないが小さなことから中国人と朝鮮人が反目し、統制組合の前で、中国人約三百人と朝鮮人約四百人が衝突しそうになつた。
たがいにトツパキ・スコツプ・マサカリのようなものを手にもつていた。集まつた人数から見ても、小さな戦争が起きるような不穏な空気につつまれていた。当時の警察力ではどうすることもできない状熊であつた。この事件は、中国人が朝鮮人ヘの代表をつれてきて、陳謝させることによつて、事なきを得た模様である。
その他こぜり合い程度のものはしぱしぱあつたが.GHQのMPが入つてきて、調停して以来下火となつた。
彼ら中国人や朝鮮人は、その年十一月から十二月にかけて帰国して行つた。それいらい、上砂川のまちには外国人のこぜり合いを見ることもなくなり、一応平静に復して行つた。