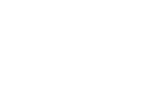ウェブサイト開設にあたって
一般財団法人 産業遺産国民会議
専務理事 加藤 康子
はじめに
「軍艦島の真実(www.gunkanjima-truth.com)」は、第二次大戦中の端島(長崎県)をはじめとする、わが国の産業と暮らしについて、歴史史料と、体験者の生の声を発信するウェブサイトである。
本ウェブサイトを立ち上げる契機については後述の通りであるが、真実を語り、誤った情報を正したいという多くの証言者のお気持ちにお応えすることができれば幸いである。また、日本政府及びユネスコ(国際連合教育科学文化機関)と連動するものではなく、一般財団法人産業遺産国民会議(以下「国民会議」)が中心となって市民と共に収集した史料を発信している。収集した史料に関しては、順次日本語のみならず、英語・韓国語に翻訳し、世界中の人々と情報を共有していく予定である。
本ウェブサイトの開設にあたり、多くの方々のご協力、温かいご支援をいただいたことに、まずは感謝の意を表したいと思う。そして、当時の記憶を呼び起こし、歴史の隙間を埋める作業に尽力してくださった証言者の方々の熱意無しには、本ウェブサイトが実現することはなかった。
「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」と端島炭坑
「明治日本の産業革命遺産」は、北は岩手から、南は鹿児島まで8県(岩手県、静岡県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県)、11市(釜石市、伊豆の国市、萩市、北九州市、中間市、大牟田市、長崎市、佐賀市、荒尾市、宇城市、鹿児島市)の広域に立地する23の遺産で構成される大型の世界遺産で、三菱重工業株式会社長崎造船所や新日鐵住金株式会社八幡製鐵所など民間企業の現役の産業設備、三池港といった大規模な工業関連施設や、廃墟として知られる端島も含んでいる。「明治日本の産業革命遺産」は、19世紀の半ば、二世紀余の長きに渡り西洋科学に門戸を閉ざしていた東洋の島国が、わずか半世紀で工業立国の土台を築き、急速に産業化した道程を時系列に沿って物語っている。すなわち、わが国の重工業(製鉄・製鋼、造船、石炭産業)におこった大きな変化、国家の質を変えた半世紀の産業化を顕している。
構成資産の1つである端島炭坑は、高島より南西3キロに位置する島で、西彼杵(にしそのぎ)海洋炭田を鉱床とする。三菱は石炭産業における近代化の先駆けとなった高島の炭鉱経営に成功したことを機に、端島の購入を決断した。同じ炭田を鉱床としているため、端島の石炭は、高島と同様に炭質がよく、高値で売れた。1891年より端島から出炭し、その6年後には端島は出炭量で高島を凌駕したが、採炭量が増加すると、採炭により出てくるボタ(廃石)で、島の周囲を埋立て拡張した。岩塊の小島を取り巻く新たな土地は、高波から島を守るため、要塞のような護岸に囲まれた。最盛期、端島は世界で最も人口過密な炭鉱コミュニティであった。
1900年、端島に灯が点灯した。エネルギー革命により電化し、電動巻揚機が導入された。端島では海底深く安定的に掘進し、採炭ができるようになった。やがて端島は世界有数の海洋炭坑に成長した。端島の海底での採炭の経験と技術によって、三菱は近代炭鉱経営の基礎を築き、三池を含む全国の炭鉱、さらにはアジアの炭鉱へと技術は伝播していった。端島はそのシルエットが「戦艦土佐」に似ていることから“軍艦島”と呼ばれるようになった。戦後も操業を続け、わが国産業の復興を支えたが、石炭から石油にエネルギー転換が進んだことにより、端島炭坑は1974年1月に閉山に追い込まれた。現在は廃墟となり、長崎市が管理している。
ユネスコ世界遺産委員会での課題
「明治日本の産業革命遺産」は、2015年7月、ドイツのボンで開催された第39回ユネスコ世界遺産委員会において、世界文化遺産に登録された。ユネスコ世界遺産委員会は、先述の「明治日本の産業革命遺産」の世界遺産価値は認めたものの、決議で8項目の課題を提示した。また、政府は日本代表団のステートメント*に留意し、世界遺産価値の対象期間外である第二次大戦中の朝鮮半島出身者の戦時徴用の展示を含むインタープリテーション戦略を準備することになった。なお、日本政府は、2017年11月30日、ユネスコ世界遺産委員会センターに8項目の課題に関する進捗状況を報告している。
(*http://www.mofa.go.jp/mofaj/pr_pd/mcc/page3_001285.html)
なぜ第二次大戦中の端島が問題になったのか?
ボンの世界遺産委員会における決議にいたるまでの背景には、登録を巡って韓国政府並びに同国の市民団体の凄まじい反対運動があった。市民団体は、端島を表紙の写真に使用した「盗まれた国、拉致された人々」という小冊子、「目覚めよユネスコ、目覚めよ世界、目覚めよ人類」と書かれたパンフレット、「ユネスコは良心の呵責に耐えられるのか」といったチラシを大量に配布した。配布された文書には生々しい写真も掲載されていた。真偽や出典が不明なものも多かったにもかかわらず、それらの写真により「端島は地獄島である」という印象が世界に広がった。こうした激しい宣伝活動により、世界各国から参加した代表団は、自ずと本来の「明治日本の産業革命遺産」の世界遺産価値から、「第二次大戦中の産業労働」に視点を移すことになり、中でも端島炭坑に世界の注目が集まった。
端島炭坑における朝鮮半島出身者の労働が、まるで歴史の暗部であるかのような認識が広く拡散した。そのことを、登録後の南ドイツ新聞の記事(2015年7月6日付)が物語っている。同紙は、「軍艦島と呼ばれていた端島において、強制労働者は苦しめられた。大戦中はもともとの日本人労働者は安全な場所に移され、中国と韓国の強制労働者に代わった」「(中国や韓国の強制労働者)1000人以上がこの島で死んだ」「(中国や韓国の)強制労働者の死体は海か廃坑に投げ入れられた」などと書いた。宣伝活動がドイツ国内に与えた影響をうかがわせる一文であった。
この記事は私たちが本ウェブサイトのための情報収集・整理を手掛ける強い動機の一つになった。それから2年半、「戦時中の端島はどのような様子だったのか」という記憶を埋めるための取材・調査活動を進めた。情報の収集・整理を進める中で、集まった貴重な歴史資料や証言を国内外に広く提供し、多くの人々に「歴史の真実」を考えていただく必要性を感じ、国民会議の理事や評議員と協議し、本ウェブサイトを開設することを決意した。
ボンから帰国して
ボンから帰国すると、さっそく戦時中の端島の労働について書かれたいくつかの本を手に取り、熟読することにした。まずは『筑豊・軍艦島』(林えいだい、弦書房)と、『軍艦島に耳を澄ませば―端島に強制連行された朝鮮人・中国人の記録』(長崎在日朝鮮人の人権を守る会、社会評論社)、『原爆と朝鮮人』(長崎在日朝鮮人の人権を守る会)を手に取り、韓国側の主張の原点を紐解いた。それらに記載された証言はいずれも、ボンの世界遺産委員会で流布された資料の「軍艦島は地獄島」という主張を裏付けるような虐待と過酷な労働の証言であった。ただ、具体的な作業現場の施設や、作業内容、生活風景については細部に曖昧なところがあり、正確な情報が欠けていた。
そこで私は可能な限り一次史料を収集することにした。だが関係者にあたったところ、一次史料が保管されている場所は拡散しており、また多くが消失し完全に残ってはいなかった。それでも周辺の関連資料を集め、一枚一枚ページをめくることを心がけた。二次史料の収集も行った。二次史料は整理の過程で運動論が展開されているものが多く、企業の加害責任を追及するスタンスで書かれたものが大半であった。被害性を強調したものについては、できる限り丁寧に目を通すことにした。
情報の収集が進むにつれ、70余年前の戦時中における産業の現場の記憶、住民や関係者の誰もが戦禍のなかで死にものぐるいで増産体制を支えた端島炭坑の職場と暮らしの記憶は、まだ十分に整理されていないと感じ、端島元島民の証言を収録することにした。
戦時中を覚えている人はいずれもご高齢で、記憶の糸をたどれる方々にコンタクトをとるには時間がかかった。数人の端島元島民が中心となり、昔の年賀状から友人を紹介してくれた。当時の仲間は、全国に散らばっており、音信が途絶えていた人に連絡をとってみると老人ホームに入所されている方、寝たきりの方、記憶が不確かな方、鬼籍に入られている方もいた。90歳近くになると、インタビュー時にはとてもお元気であっても、後に体調を崩される方もおり、70余年前のことを思い出すことを楽しむ人もいれば、それが大変なストレスになり、負担になる方もいた。
だが多くの元島民はひとたび胸襟を開くと、故郷への郷土愛から、いずれも積極的に話をしはじめた。話をするうちに、最初は口数が少なかった人でも、一度目よりは二度目、二度目よりは三度目と話がはずんでくる。何度も足を運ぶ中で、また数人が寄り合う中で、齢を重ねて風化し、断片的になっていた記憶も、パズルが埋まっていくように、当時の情景が色鮮やかに蘇っていった。そういった対話を通して、元端島島民たちによる「真実の歴史を追求する端島島民の会」が発足し、端島の真実を探求する活動はいよいよ活発になった次第である。本ウェブサイトを見ていただくことで、彼らの証言から端島の労働と暮らしに対する理解が深まれば幸いである。
国民会議においては、限られたマンパワーで、現在も一次史料を収集中であり、整理された史料を今後段階的に開示することを予定している。史料の整理が進めば、随時それらを日本語、英語、韓国語で発信していく所存である。

加藤 康子(Koko Kato)
「明治日本の産業革命遺産」世界遺産協議会コーディネーター、山本作兵衛ユネスコ世界記憶遺産プロジェクトコーディネーター
「明治日本の産業革命遺産」産業界プロジェクトチームコーディネーター、
「明治日本の産業革命遺産登録推薦書」、
「明治日本産業革命遺産推薦書ダイジェスト版」、
公式の明治日本の産業革命遺産関連書籍、DVD、WEBサイトの主筆並びにディレクター
元筑波大学客員教授(平成26年4月1日~平成28年3月31日)
一般財団法人産業遺産国民会議 専務理事。
2015年7月より内閣官房参与。
慶應義塾大学文学部卒業。
国際会議通訳を経て、米国CBSニュース東京支社に勤務。ハーバードケネディスクール大学院都市経済学修士課程(MCRP)を修了後、日本にて起業。
国内外の企業城下町の産業遺産研究に取り組む。
著書「産業遺産」(日本経済新聞社、1999年)ほか、世界の企業城下町のまちづくりを鉱山・製鐵の街を中心に紹介。
「エコノミスト」「学塔」「地理」など各誌に論文、エッセーを執筆。