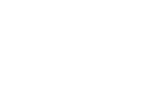人口密度日本一だった端島での生活
戦時の石炭需要を支えた端島の人々の生活は、日本初の鉄筋コンクリート造の高層集合住宅での暮らしなど端島独特のものでした。ここでは、当時の端島の生活の概要をご紹介します。
人口密度日本一の島
人口密度日本一だった端島には、炭鉱の職員とその家族、坑内夫・坑外夫とその家族ら約3200人が、日本初の鉄筋コンクリート造の高層集合住宅を中心に狭い島内で暮らしていました。 24時間二交代制(戦後は三交代制)だった端島炭坑は、まさに不夜城で、島には炭鉱の生産施設の他、事務所、住宅はもちろん、病院や学校、食堂、共同浴場、神社、寺、商店、映画館、旅館、遊郭など、生活に必要なあらゆる施設が揃い、撞球場など娯楽施設もありました。「端島銀座」と呼ばれた青空市場では、対岸の野母半島高浜から農漁民が行商に訪れ、雨の日でも賑わったそうです。
潮が降る町
海が荒れると護岸にぶつかった波しぶきがアパートを超えて降り注ぐ「潮降り町」と名付けられた一画もありました。昭和2年に建てられた煉瓦造2階建て400席の映画館は、「昭和館」と名付けられましたが、波しぶきが激しい場所にあったことから「島一番の汐降りどころで、屋根にザンブと汐が鳴る」と雑誌(「主婦の友・3月号」昭和31年3月1日発行)に記されています。
昭和8年(1933年)に端島を訪れた作家の江見水蔭は著書『水蔭行脚全集』第5巻に、こう記しています。「竜宮城の如く各建築の電灯が輝き渡り、海上デパートかと疑われた」「神社、学校、寺院、劇場、料理店まである等、正に洋上の理想郷。現実の極楽島」「坑夫なども昔の如き荒い気分はなく、主義者(=左翼思想の人々)が来ても、救護救済機関が整備しているので、爪も立たぬ」。
日本初の高層住宅
端島のシンボルは、日本初の鉄筋コンクリート造の高層集合住宅です。大正5年(1916年)に建てられた7階建の巨大なロの字型アパート(30号棟)では、正方形の中庭を囲むように六畳一間の住居が各階に並び、あわせて145戸がありました。カマドは各戸にありましたが、流しは吹き抜け廊下に設けられた共用で、洗い物はそこで行いました。大正7年(1918年)に建てられた「日給社宅」と呼ばれた9階建は、総床面積1万2千平方メートル、255戸のさらに巨大な高層集合住宅です。各戸に居室は二間あり、台所にはカマドだけでなく流しも備えつけられました。通路などの共用空間は、炊事や洗濯のほか、夕涼みや子供の遊び場など住人たちの交流の場として機能しました。なお「日給社宅」の1階部分の半地下には130人の朝鮮人労働者が住んでいたと昭和11年10月発行の『婦人之友』には記載されています。
貴重な水と共同体意識
端島では、生活用水は貴重なものでした。真水は給水船で島まで運ばれ、最も高い場所にあった貯水タンクから配水されました。各戸では水がめを据え、水を大切に扱いました。日給社宅では、各階に真水用と海水用の二つの水栓が設置され、時間決めで給水されました。真水は桶二杯二斗が一銭五厘で販売されました。海水は無料だったので坑夫の家では洗濯や掃除はもとより、食器洗いや米とぎまでも海水を使っていたそうです。海が荒れると船が欠航するため、真水の使用は厳しく制限されました。
共同浴場は島内に3か所あり、1つは事業所内にある坑内に入った人のためのもの、1つは9階建の日給社宅にあった坑夫の家族用、1つは職員家族用でした。「荒れはじめると真先に海水に代わるのはお風呂」(「婦人之友」昭和11年10月発行)と記されています。こうした水にまつわる厳しい環境が、端島の共同体意識を高めた要因でもあります。
島の子供たちと学校教育
端島には子供も多く暮らしていました。明治26年(1893年)11月3日には、三菱社が端島小学校を開校させ、後に公立学校となります。「高浜村現勢概要」(大正15年6月30日発行)には大正15年(1926年)4月1日現在、端島尋常高等小学校には、尋常科6学級、高等科1学級、普通教室7室、裁縫室1室、理科室1室、在籍児童者数376 人と記されています。昭和9年(1934年)には新校舎が完成。昭和16年(1941年)には高浜村立尋常高等小学校は端島国民学校に改称されました。当時の端島を知る人々によれば、朝鮮人労働者の子供も区別なく通学していたそうです。
戦時中の厳しい食糧事情
端島の戦時中の配給事情は、戦況が悪化するに従い物資不足に陥った。米の代わりに配給された食糧は、油採取用の大豆を搾った残りカスで「脱脂大豆」と呼ばれました。当時を知る端島の人々は、「脱脂大豆」によってよく下痢をしたと証言しています。朝鮮人労働者の証言にも同様のものがみられますが、当時の島全体の食糧事情の厳しさをよくあらわしています。