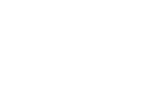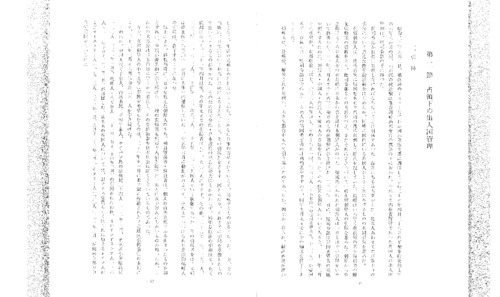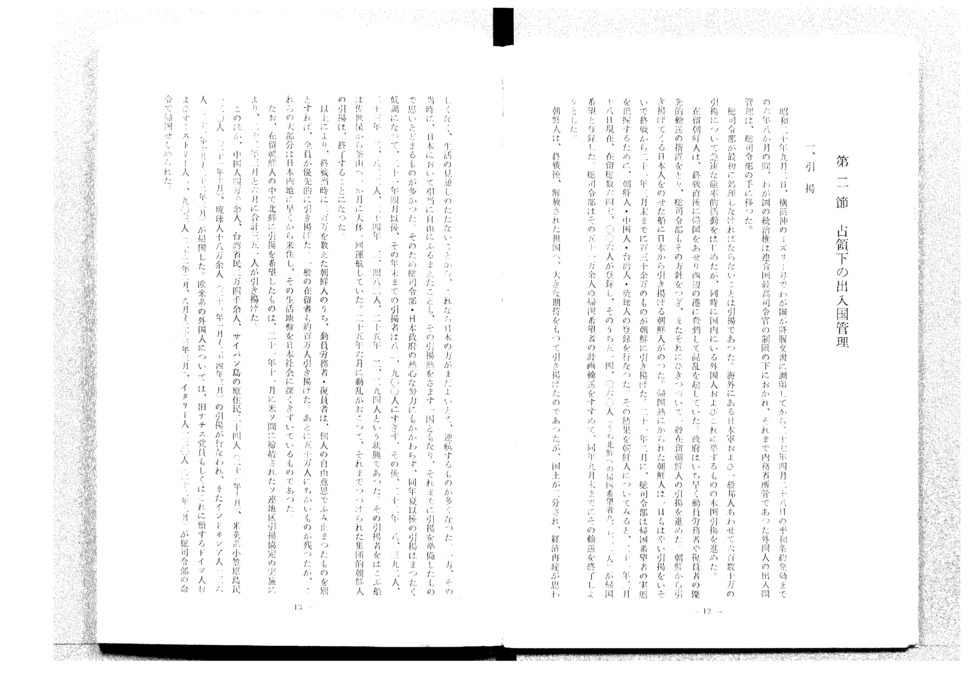法務省入国管理局 出入国管理白書出入国管理とその実態 昭和34年
分類コード:II-03-06-001
発行年:1959年
第二章 出入国管理の沿革と現在の機構 第二節 占領下の出入国管理 一 引揚
法務省入国管理局が年一回発行している報告。第2章では、終戦以降の内地在住朝鮮人の朝鮮への送還に関して、経緯と概観を述べている。
- 著作者:
- 法務省入国管理局
Page 1
法務省入国管理局 出入国管理白書出入国管理とその実態 昭和34年
第二節 占領下の出入国管理
一、引揚
昭和二十年九月二日、横浜沖のミズリー号でわが国が降服文書に調印してから二十七年四月二十八日の平和条約発効までの六年八か月の間、わが国の統治権は連合国最高司令官の制限の下におかれ、それまで内務省所管であつた外国人の出人国管理は、総司令部の手に移った。
総司令部が最初に処理しなければならないことは引揚であつた。海外にある日本軍および一般邦人あわせて六百数十万の引揚について急速な能率的活動をはじめたが、同時に国内にいる外国人およびこれに準じるものの本国引揚を進めた。
在留朝鮮人は、終戦直後に帰国をあせり西辺の港に殺到して混乱を起していた。政府はいち早く動員労務者や復員者の優先的輸送の措置をとり、総司令部もその方針をつぎ、またそれにひきつづいて一般在留朝鮮人の引揚を進めた。朝鮮から引き揚げてくる日本人をのせた船に日本から引き揚げる朝鮮人がのつた。帰国熱にかられた朝鮮人は一日もはやい引揚をいそいで終戦から二十一年三月末までに百三十余万のものが朝鮮に引き揚げた。二十一年二月に、総司令部は帰国希望者の実態を把握するために、朝鮮人・中国人・台湾人・琉球人の登録を行つた。その結果を朝鮮人についてみると、二十一年三月十八日現在、在留総数六四七、〇〇六人が登録し、そのうち五一四、〇六〇人(うち北鮮への帰国希望者九、七〇一人)が帰国希望と登録した。総司令部はその五十一万余人の帰国希望者の計画輸送をすすめて、同年九月末までにその輸送を終了しようとした。
朝鮮人は、終戦後、解放された祖国へ、大きな期待をもつて引き揚げたのであつたが、国土が二分され、経済再建が思わしくなく、生活の見通しのたたないことから、これなら日本の方がまだよいとて、逆航するものが多くなつた。一方、その当時に、日本において相当に自由にふるまえたことも、その引揚熱をさます一因ともなり、それまでに引揚を準備Lたもので思いとどまるものが多かつた。そのため総司令部・日本政府の熱心な努力にもかかわらず、同年夏以降の引揚はまつたく低調になつて、二十一年四月以後、その年末までの引揚者は八二、九〇〇人にすぎず、その後、二十二年 八、三九二人、二十三年 二、八二二人、二十四年 三、四八二人、二十五年 二、二九四人という状態であつた。その引揚者をはこぶ船は佐世保から釜山へ一か月に大体一回運航していた。二十五年六月に動乱かおこつて、それまでつづけられた集団的朝鮮人の引揚は、終了することになつた。
以上により、終戦当時に二百万を数えた朝鮮人のうち、動員労務者・復員者は、個人の自由意思でふみ止まつたものを別とすれば、全員が優先的に引き揚げた。一般の在留者も約百万人引き揚げた。あとに五十万人にちかいものか残つたが、これらの大部分は日本内地に早くから来住し、その生活地盤を日本社会に深くきずいているものであつた。
なお、在留朝鮮人の中で北鮮に引揚を希望したものは、二十一年十一月に米ソ間に締結されたソ連地区引揚協定の実施により、二十二年三月と六月に合計三五一人が引き揚げた。
このほか、中国人四万千余人、台湾省民二万四千余人、サイパン島の原住民二十四人(二十一年十月)、米英系小笠原島民一二〇人(二十一年十月)、琉球人十八万余人(二十一年一月~二十四年三月)の引揚が行なわれ、またインドネシア人一三六人(二十一年十月~二十二年三月)が帰国した。欧米系の外国人については、旧ナチス党員もしくはこれに類するドイツ人およびオーストーリー人一、九〇三人(二十二年二月~二十三年三月)、イタリー人(二十二年二月)が総司令部の命令で帰国せしめられた。