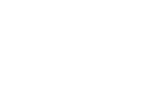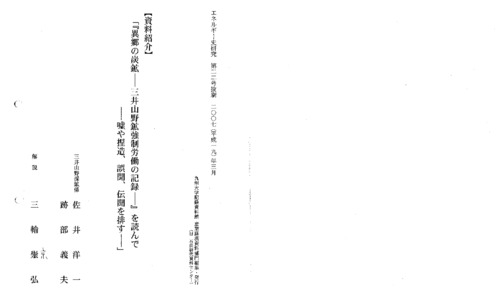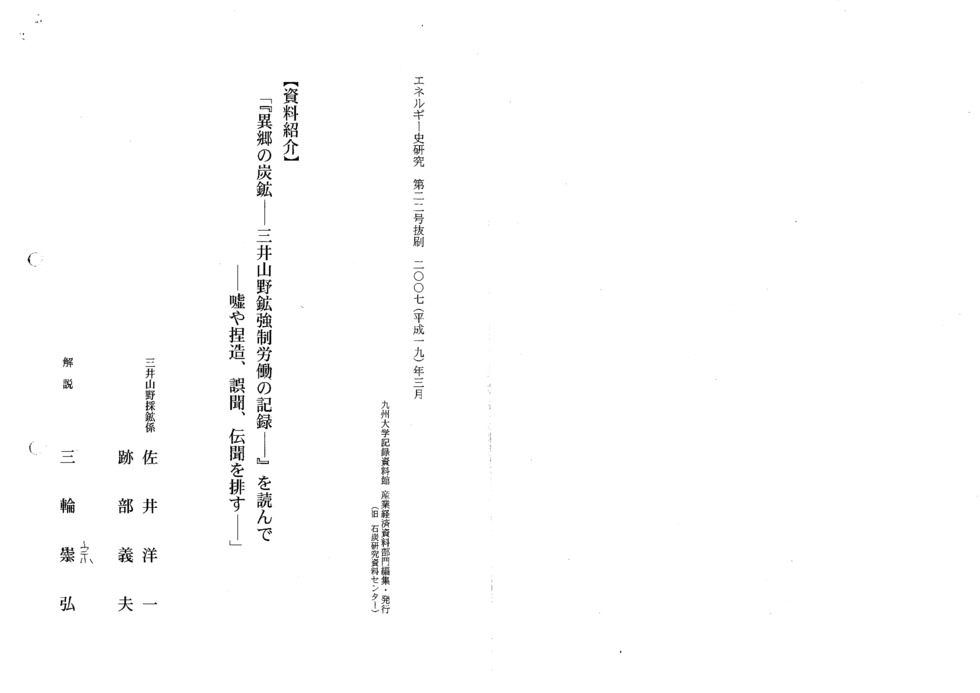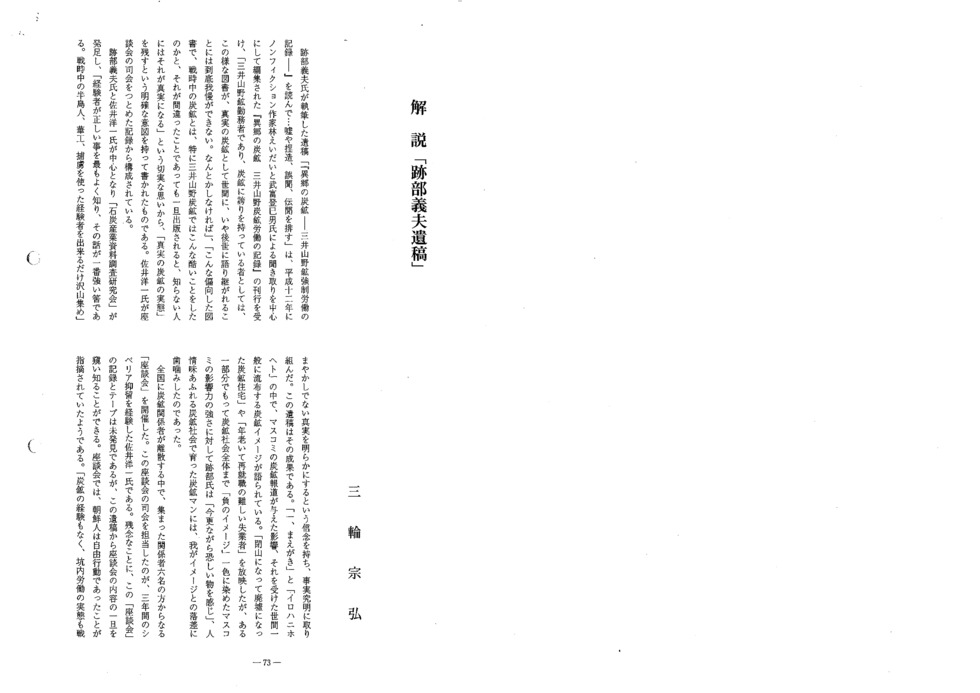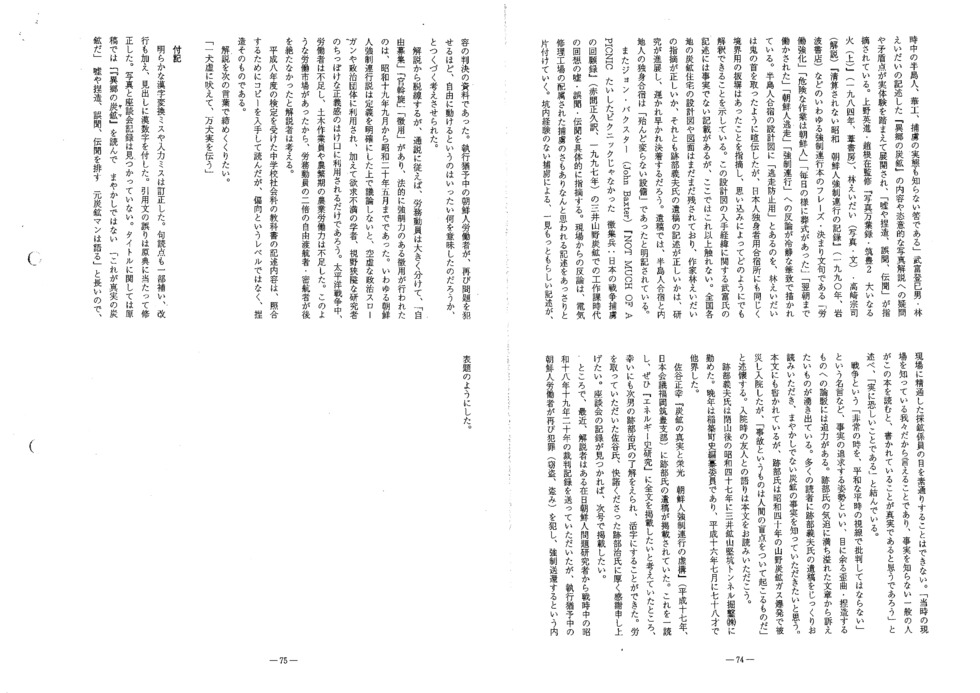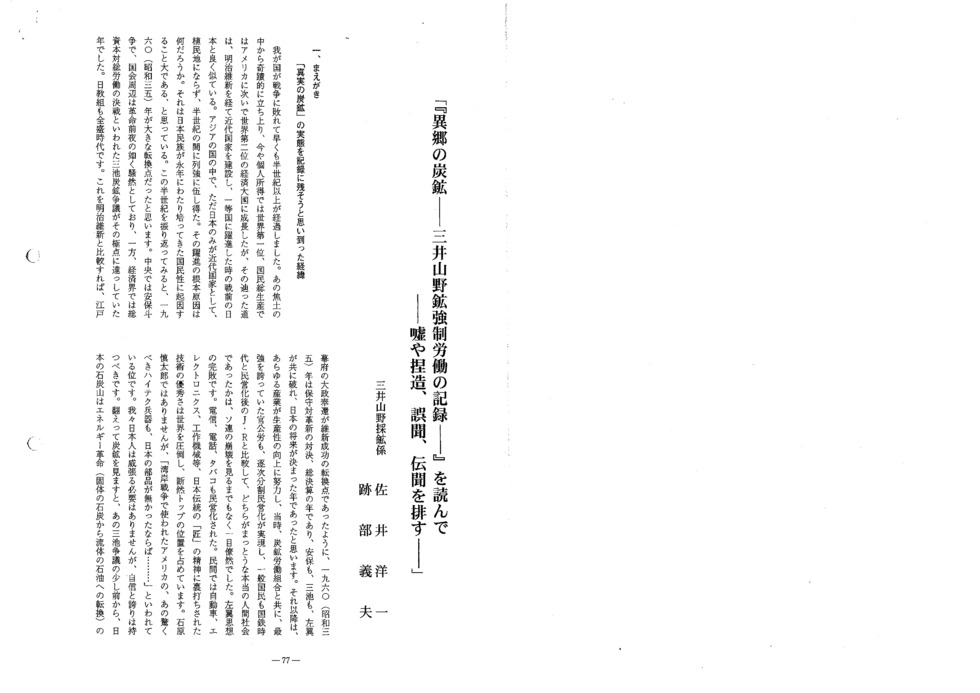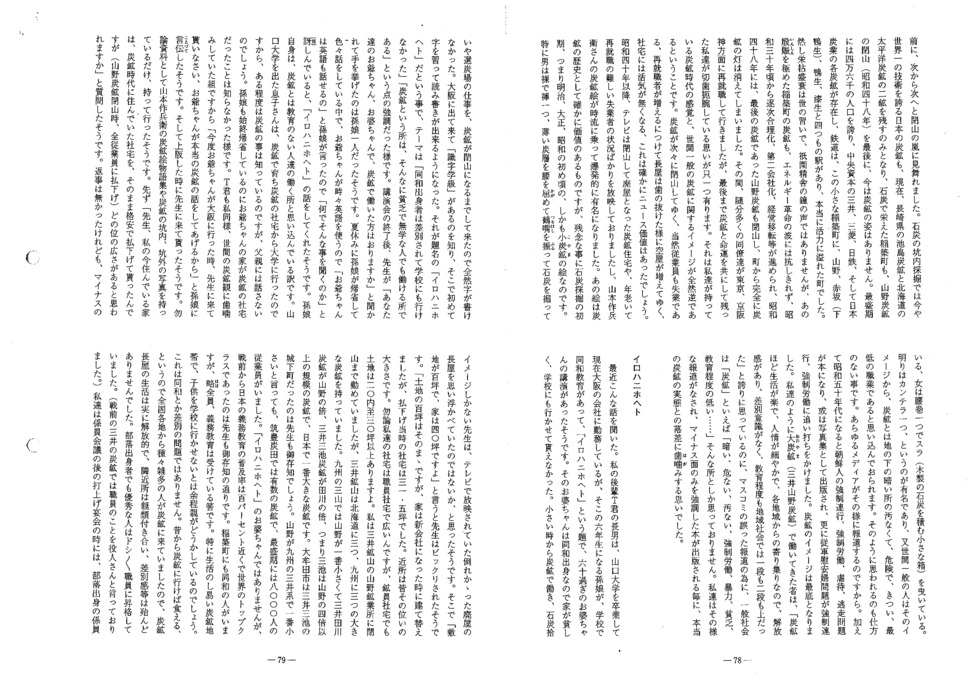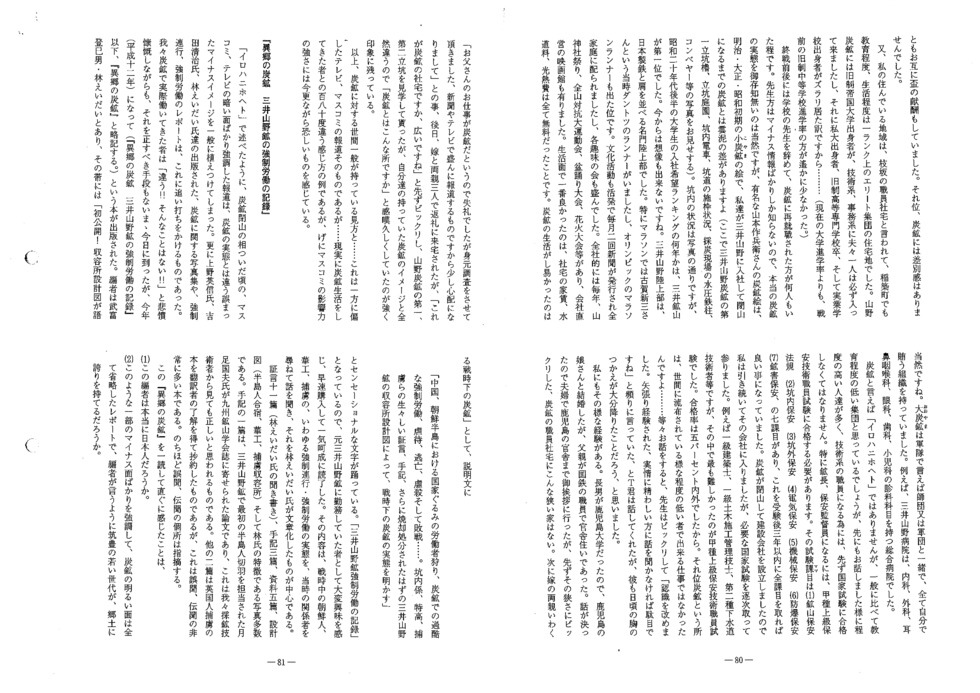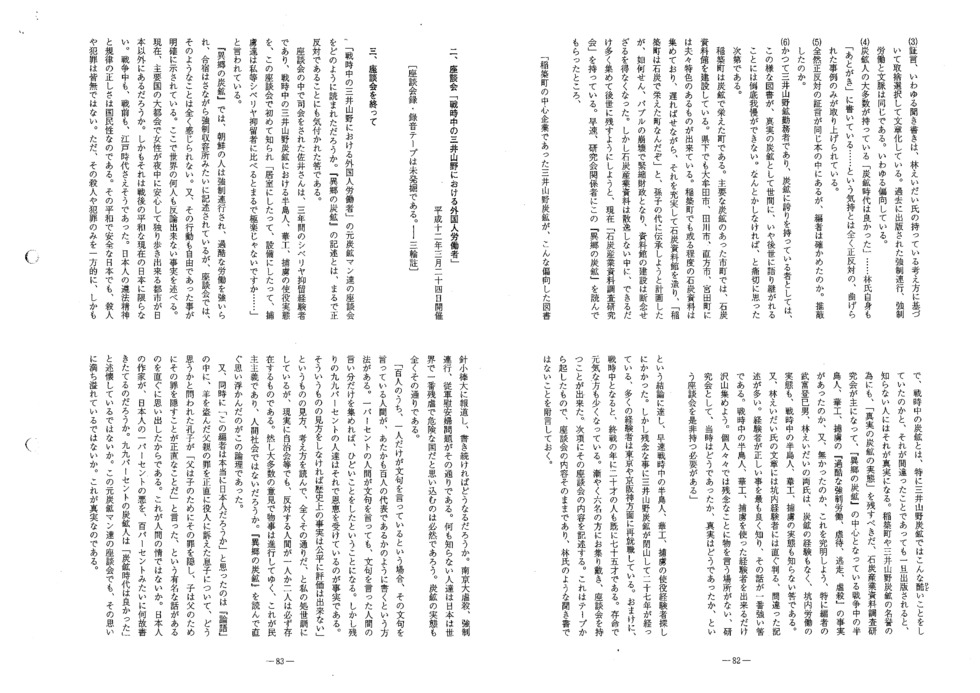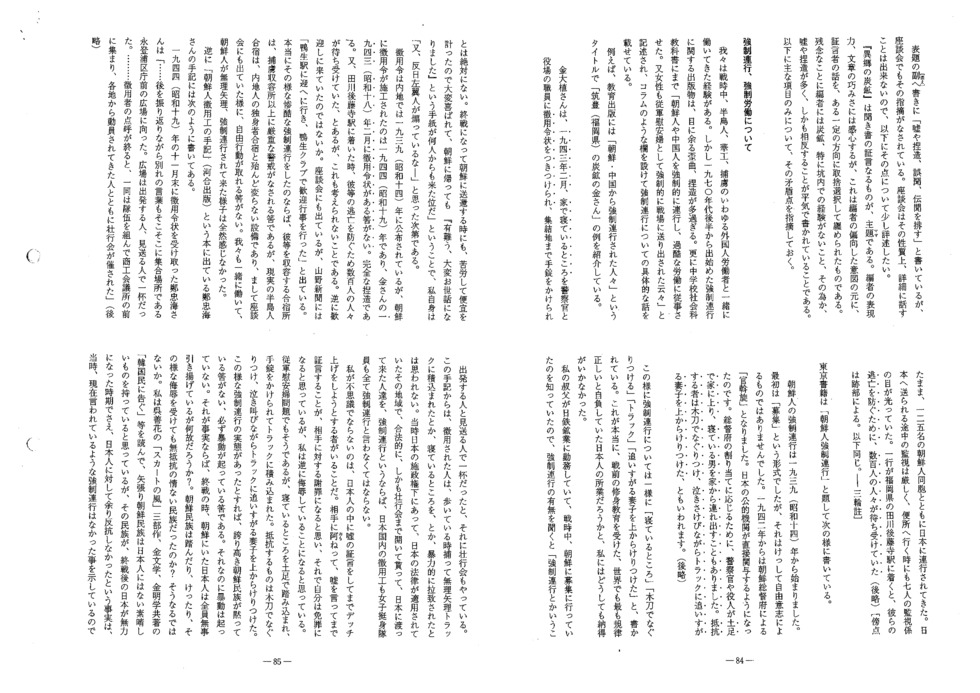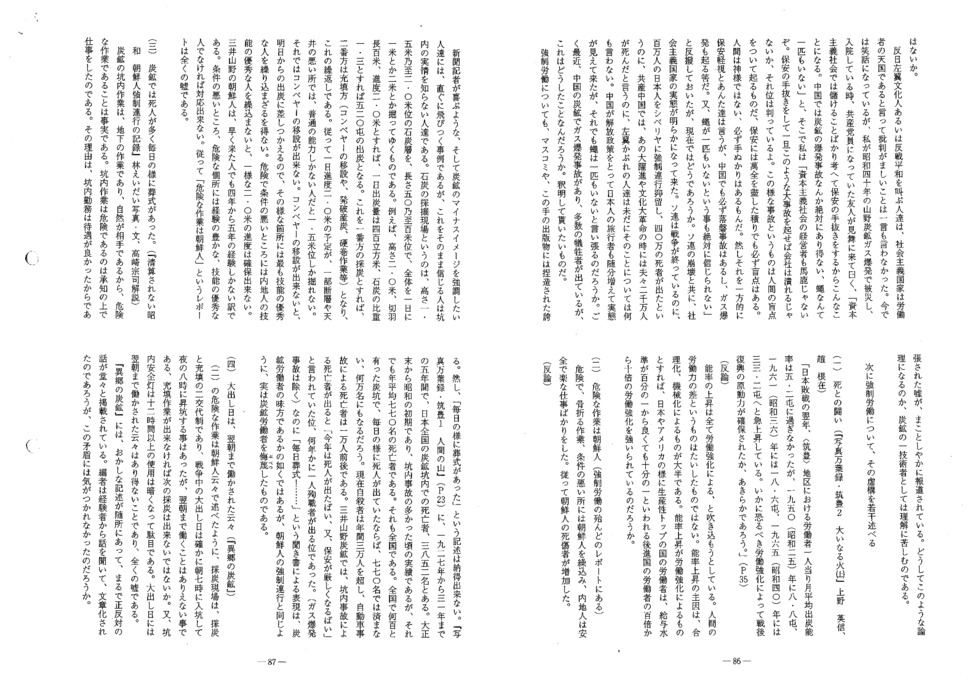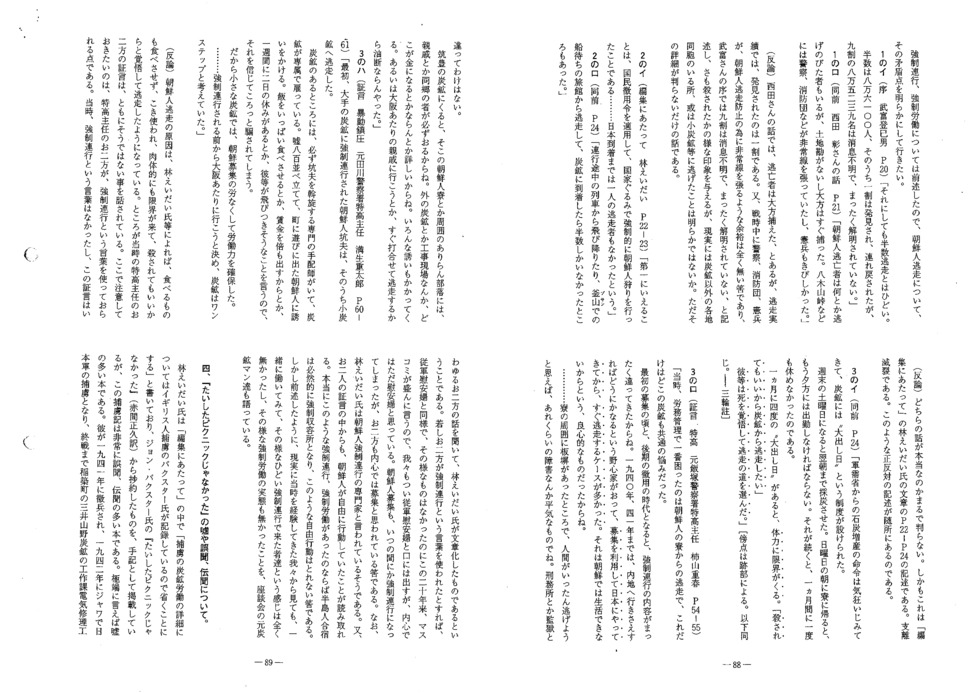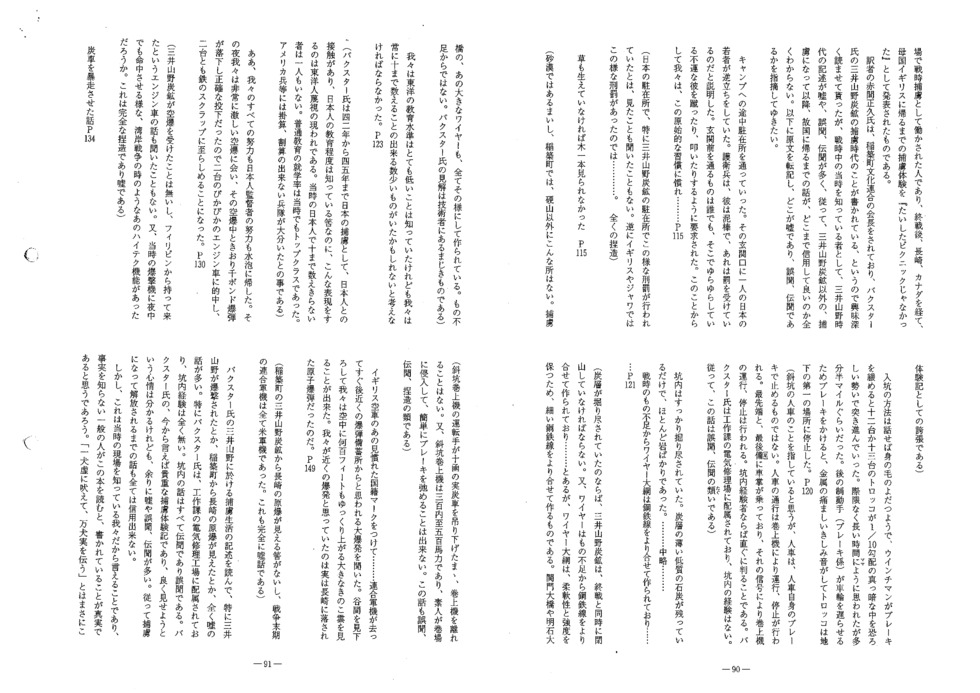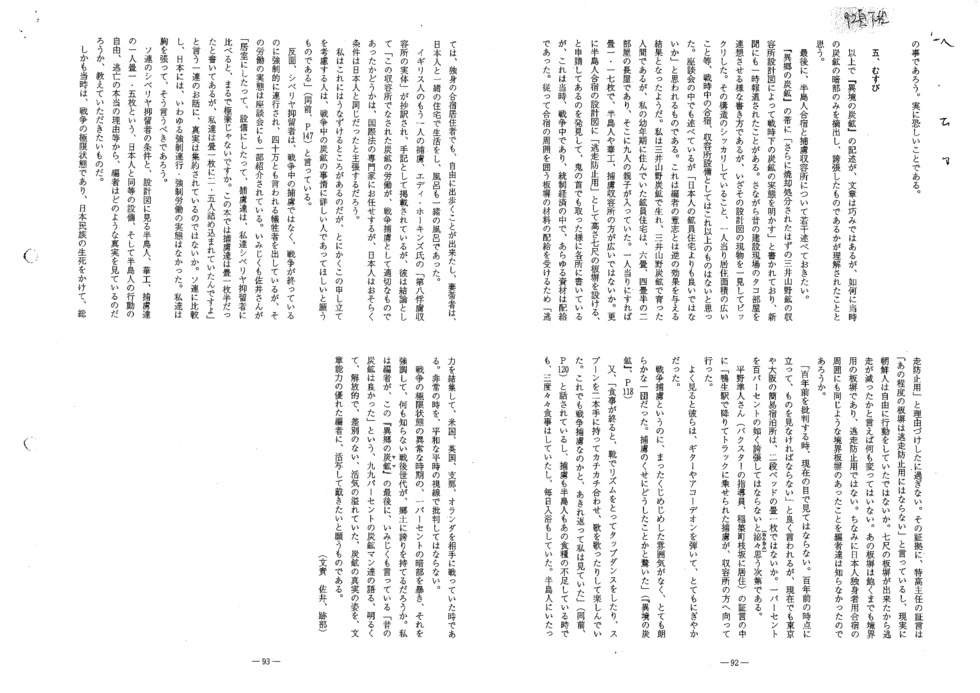Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
エネルギー史研究 第二二号抜刷 二〇〇七(平成一九)年三月
九州大学記録資料館 産業経済資料部門編集・発行(旧 石炭研究資料センター)
【資料紹介】
「『異郷の炭鉱――三井山野鉱強制労働の記録――』を読んで――嘘や握造、誤聞、伝聞を排す――」
三井山野採鉱係 佐井洋一
跡部義夫
解説 三輪崇(ママ)弘
解説「跡部義夫遺稿」
三輪宗弘
跡部義夫氏が執筆した遺稿「『異郷の炭鉱――三井山野鉱強制労働の記録――』を読んで…嘘や捏造、誤聞、伝聞を排す」は、平成十二年にノンフィクション作家林えいだいと武富登巳男氏による聞き取りを中心にして編集された『異郷の炭鉱 三井山野炭鉱労働の記録』の刊行を受け、「三井山野鉱勤務者であり、炭鉱に誇りを持っている者としては、この様な図書が、真実の炭鉱として世間に、いや後世に語り継がれることには到底我慢ができない。なんとかしなければ」、「こんな偏向した図書で、戦時中の炭鉱とは、特に三井山野炭鉱ではこんな酷いことをしたのかと、それが間違ったことであっても一旦出版されると、知らない人にはそれが真実になる」という切実な思いから、「真実の炭鉱の実態」を残すという明確な意図を持って書かれたものである。佐井洋一氏が座談会の司会をつとめた記録から構成されている。
跡部義夫氏と佐井洋一氏が中心となり「石炭産業資料調査研究会」が発足し、「経験者が正しい事を最もよく知り、その話が一番強い筈である。戦時中の半島人、華工、捕虜を使った経験者を出来るだけ沢山集め」まやかしでない真実を明らかにするという信念を持ち、事実究明に取り組んだ。この遺稿はその成果である。「一、まえがき」と「イロハニホヘト」の中で、マスコミの炭鉱報道が与えた影響、それを受けた世間一般に流布する炭鉱イメージが語られている。「閉山になって廃墟になった炭鉱住宅」や「年老いて再就職の難しい失業者」を放映したが、ある一部分でもって炭鉱社会全体まで「負のイメージ」一色に染めたマスコミの影響力の強さに対して跡部氏は「今更ながら恐しい物を感じ」、人情味あふれる炭鉱社会で育った炭鉱マンには、我がイメージとの落差に歯噛みしたのであった。
全国に炭鉱関係者が離散する中で、集まった関係者六名の方からなる「座談会」を開催した。この座談会の司会を担当したのが、三年間のシベリア抑留を経験した佐井洋一氏である。残念なことに、この「座談会」の記録とテープは未発見であるが、この遺稿から座談会の内容の一旦(ママ)を窺い知ることができる。座談会では、朝鮮人は自由行動であったことが指摘されていたようである。「炭鉱の経験もなく、坑内労働の実態も戦時中の半島人、華工、捕虜の実態も知らない筈である」武富登巳男・林えいだいの記述した『異郷の炭鉱』の内容や恣意的な写真解説への疑問や矛盾点が実体験を踏まえて展開され、「嘘や捏造、誤聞、伝聞」が指摘されている。上野英進・趙根在監修『写真万葉録・筑豊2 大いなる火(上)』(一九八四年、葦書房)、林えいだい(写真・文)・高崎宗司(解説)「清算されない昭和 朝鮮人強制連行の記録」(一九九〇年、岩波書店)などのいわゆる強制連行本のフレーズ・決まり文句である「労働強化」「危険な作業は朝鮮人」「毎日の様に葬式があった」「翌朝まで働かされた」「朝鮮人逃走」「強制連行」への反論が冷静な筆致で描かれている。半島人合宿の設計図に「逃走防止用」とあるのを、林えいだいは鬼の首を取ったように喧伝したが、日本人独身者用合宿所にも同じく境界用の板塀はあったことを指摘し、思い込みによってどのようにでも解釈できることを示している。この設計図の入手経緯に関する武富氏の記述には事実でない記載があるが、ここではこれ以上触れない。全国各地の炭鉱住宅の設計図や図面はまだまだ残されており、作家林えいだいの指摘が正しいか、それとも跡部義夫氏の遺稿の記述が正しいかは、研究が進展し、遅かれ早かれ決着するだろう。遺稿では、半島人合宿と内地人の独身合宿は「殆んど変らない設備」であったと明記されている。
またジョン・バクスター(John Baxter)『NOT MUCH OF A PICNIC たいしたピクニックじゃなかった 徴集兵:日本の戦争捕虜の回顧録』(赤間正久訳、一九九七年)の三井山野炭鉱での工作課時代の回想の嘘・誤聞・伝聞を具体的に指摘する。現場からの反論は、電気修理工場の配属された捕虜のさもありなんと思われる記述をあっさりと片付けていく。坑内経験のない捕虜による、一見もっともらしい記述が、現場に精通した採鉱係員の目を素通りすることはできない。「当時の現場を知っている我々だから言えることであり、事実を知らない一般の人がこの本を読むと、書かれていることが真実であると思うであろう」と述べ、「実に恐しいことである」と結んでいる。
戦争という「非常の時を、平和な平時の視線で批判してはならない」という名言など、事実の追求する姿勢といい、目に余る歪曲・捏造するものへの論駁には迫力がある。跡部氏の気迫に満ち溢れた文章から訴えたいものが湧き出ている。多くの読者に跡部義夫氏の遺稿をじっくりお読みいただき、まやかしでない炭鉱の事実を知っていただきたいと思う。本文にも書かれているが、跡部氏は昭和四十年の山野炭鉱ガス爆発で被災し入院したが、「事故というものは人間の盲点をついて起こるものだ」と述懐する。入院時の友人との語りは本文をお読みいただこう。
跡部義夫氏は閉山後の昭和四十七年に三井鉱山堅坑トンネル掘鑿㈱に勤めた。晩年は稲築町史編纂委員であり、平成十六年七月に七十八才で他界した。
佐谷正幸『炭鉱の真実と栄光 朝鮮人強制連行の虚構』(平成十七年、日本会議福岡筑豊支部)に跡部氏の遺稿が掲載されていた。これを一読し、ぜひ『エネルギー史研究』に全文を掲載したいと考えていたところ、幸いにも次男の跡部治氏の了解をえられ、活字にすることができた。労を取っていただいた佐谷氏、快諾くださった跡部治氏に厚く感謝申し上げたい。座談会の記録が見つかれば、次号で掲載したい。
ところで、最近、解説者はある在日朝鮮人問題研究者から戦時中の昭和十八年十九年二十年の裁判記録を送っていただいたが、執行猶予中の朝鮮人労働者が再び犯罪(窃盗、盗み)を犯し、強制送還するという内容の判決の資料であった。執行猶予中の朝鮮人労働者が、再び問題を犯せるほど、自由に動けるというのはいったい何を意味したのだろうか、とつくづく考えさせられた。
解説から脱線するが、通説に従えば、労務動員は大きく分けて、「自由募集」「官斡旋」「徴用」があり、法的に強制力のある徴用が行われたのは、昭和十九年九月から昭和二十年五月までであった。いわゆる朝鮮人強制連行説は定義を明確にした上で議論しないと、空虚な政治スローガンや政治団体に利用され、加えて欲求不満の学者、視野狭隘な研究者のちっぽけな正義感のはけ口に利用されるだけであろう。太平洋戦争中、労働者は不足し、土木作業員や農繁期の農業労働力は不足した。このような労働市場があったから、労務動員の二倍の自由渡航者・密航者が後を絶たなかったと解説者は考える。
平成八年度の検定を受けた中学校社会科の教科書の記述内容は、照合するためにコピーを入手して読んだが、偏向というレベルではなく、捏造そのものである。
解説を次の言葉で締めくくりたい。
「一犬虚に吠えて、万犬実を伝う」
付記
明らかな漢字変換ミスや入力ミスは訂正した。句読点も一部補い、改行も加え、見出しに漢数字を付した。引用文の誤りは原典に当たって修正した。写真と座談会記録は見つかっていない。タイトルに関しては原稿では「『異郷の炭坑』を読んで まやかしではない 「これが真実の炭鉱だ」嘘や捏造、誤聞、伝聞を排す 元炭鉱マンは語る」と長いので、表題のようにした。
「『異郷の炭鉱――三井山野鉱強制労働の記録――』を読んで――嘘や握造、誤聞、伝聞を排す――」
三井山野採鉱係 佐井洋一
跡部義夫
一、まえがき
「真実の炭鉱」の実態を記録に残そうと思い到った経緯
我が国が戦争に敗れて早くも半世紀以上が経過しました。あの焦土の中から奇蹟的に立ち上り、今や個人所得では世界第一位、国民総生産ではアメリカに次いで世界第二位の経済大国に成長したが、その辿った道は、明治維新を経て近代国家を建設し、一等国に躍進した時の戦前の日本と良く似ている。アジアの国の中で、ただ日本のみが近代国家として、植民地にならず、半世紀の間に列強に伍し得た。その躍進の根本原因は何だろうか。それは日本民族が永年にわたり培ってきた国民性に起因すること大である、と思っている。この半世紀を振り返ってみると、一九六〇(昭和三五)年が大きな転換点だったと思います。中央では安保斗争で、国会周辺は革命前夜の如く騒然としており、一方、経済界では総資本対総労働の決戦といわれた三池炭鉱争議がその極点に達っしていた年でした。日教組も全盛時代です。これを明治維新と比較すれば、江戸幕府の大政奉還が維新成功の転換点であったように、一九六〇(昭和三五)年は保守対革新の対決、総決算の年であり、安保も、三池も、左翼が共に破れ、日本の将来が決まった年であったと思います。それ以降は、あらゆる産業が生産性の向上に努力し、当時、炭鉱労働組合と共に、最強を誇っていた官公労も、逐次分割民営化が実現し、一般国民も国鉄時代と民営化後のJ・Rと比較して、どちらがまっとうな本当の人間社会であったかは、ソ連の崩壊を見るまでもなく一目僚然でした。左翼思想の完敗です。電信、電話、タバコも民営化された。民間では自動車、エレクトロニクス、工作機械等、日本伝統の「匠」の精神に裏打ちされた技術の優秀さは世界を圧倒し、断然トップの位置を占めています。石原慎太郎ではありませんが、「湾岸戦争で使われたアメリカの、あの驚くべきハイテク兵器も、日本の部品が無かったならば………」といわれている位です。我々日本人は威張る必要はありませんが、自信と誇りは持つべきです。翻えって炭鉱を見ますと、あの三池争議の少し前から、日本の石炭山はエネルギー革命(固体の石炭から流体の石油への転換)の前に、次から次へと閉山の嵐に見舞れました。石炭の坑内採掘では今や世界一の技術を誇る日本の炭鉱も、現在、長崎県の池島炭鉱と北海道の太平洋炭鉱の二鉱を残すのみとなり、石炭で栄えた稲築町も、山野炭鉱の閉山(昭和四十八年)を最後に、今は炭鉱の姿はありません。最盛期には四万六千の人口を誇り、中央資本の三井、三菱、日鉄、そして日本炭業の各炭鉱が存在し、鉄道は、この小さな稲築町に、山野、赤坂(下鴨生)、鴨生、漆生と四つもの駅があり、本当に活力に溢れた町でした。然し栄枯盛衰は世の習いで、祇園精舎の鐘の声ではありませんが、あの殷賑を極めた稲築町の炭鉱も、エネルギー革命の波には抗しきれず、昭和三十年頃から逐次合理化、第二会社化、経営移転等が進められ、昭和四十八年には、最後の炭鉱であった山野炭鉱も閉山し、町から完全に炭鉱の灯は消えてしまいました。その間、随分多くの同僚達が東京、京阪神方面に再就職して行きましたが、最後まで炭鉱と命運を共にして残った私達が切歯扼腕している思いが只一つ有ります。それは私達が持っている炭鉱時代の感覚と、世間一般の炭鉱に関するイメージが全然逆であるということです。炭鉱が次々に閉山してゆく、当然従業員も失業である、再就職者が増えるにつけて長屋は歯の抜けた様に空屋が増えてゆく、社宅には活気が無くなる、これは確かにニュース価値はあったでしょう。昭和四十年以降、テレビは閉山して廃屋となった炭鉱住宅や、年老いて再就職の難しい失業者の状況ばかりを放映しておりましたし、山本作兵衛さんの炭鉱絵が時流に乗って爆発的に有名になりました。あの絵は炭鉱の歴史として確かに価値のあるものですが、残念な事に石炭採掘の初期、つまり明治、大正、昭和の初め頃の、しかも小炭鉱の絵なのです。特に男は裸で褌一つ、薄い炭層を腰を屈めて鶴嘴を振って石炭を掘っている、女は腰巻一つでスラ(木製の石炭を積む小さな箱)を曳いている。明りはカンテラ一つ、というのが有名であり、又世間一般の人はそのイメージから、炭鉱とは地の下の暗い所の汚なくて、危険で、きつい、最低の職業であると思い込んでおられます。そのように思われるのも仕方のない事です。あらゆるメディアがその様に報道するのですから。加えて昭和五十年代になると朝鮮人の強制連行、強制労働、虐待、逃走問題が本になり、或は写真集として出版され、更に従軍慰安婦問題が強制連行、強制労働に追い打ちをかけました。炭鉱のイメージは最底となりました。私達のように大炭鉱(三井山野炭鉱)で働いてきた者は、「炭鉱ほど生活が楽で、人情が細やかで、各地域からの寄り集りなので、解放感があり、差別意識がなく、教育程度も地域社会では一段も二段も上だった」と誇りに思っているのに、マスコミの誤った報道の為に、一般社会は「炭鉱」といえば「暗い、危ない、汚ない、強制労働、暴力、貧乏、教育程度の低い……」そんな所としか思っておりません。私達はその様な報道がなされ、マイナス面のみを強調した本が出版される毎に、本当の炭鉱の実態との落差に歯噛みする思いでした。
イロハニホヘト
最近こんな話を聞いた。私の後輩T君の長男は、山口大学を卒業して現在大阪の会社に勤務しているが、そこの六年生になる孫娘が、学校で同和教育があって、「イロハニホヘト」という題で、六十過ぎのお婆ちゃんの講演があったそうです。そのお婆ちゃんは同和出身なので家が貧しく、学校にも行かせて貰えなかった。小さい時から炭鉱で働き、石炭拾いや選炭場の仕事を、炭鉱が閉山になるまでして来たので全然字が書けなかった。大阪に出て来て「識字学級」があるのを知り、そこで初めて字を習って読み書きが出来るようになった。それが題名の「イロハニホヘト」だという事で、テーマは「同和出身者は差別されて学校にも行けなかった」「炭鉱という所は、そんなに貧乏で無学な人でも働ける所である」という点の強調だった様です。講演会の終了後、先生が「あなた達のお爺ちゃん、お婆ちゃんで、炭鉱で働いた方はおりますか」と聞かれて手を挙げたのは孫娘一人だったそうです。夏休みに孫娘が帰省して色々話をしている中で、お爺ちゃんが時々英語を使うので「お爺ちゃんは英語も話せるの」と孫娘が言ったので「何でそんな事を聞くのか」と訝しんでいると、「イロハニホヘト」の話をしてくれたそうです。孫娘自身は、炭鉱とは教育のない人達の働く所と思い込んでいる訳です。山口大学を出た息子さんは、炭鉱で育ち炭鉱の社宅から大学に行ったのですから、ある程度は炭鉱の事は知っているのですが、父親には話さないのでしょう。孫娘も始終帰省しているのにお爺ちゃんの家が炭鉱の社宅だったことは知らなかった様です。T君も私同様、世間の炭鉱観に歯噛みしていた組ですから「今度お爺ちゃんが大阪に行った時、先生に来て貰いなさい、お爺ちゃんが本当の炭鉱の話をしてあげるから」と孫娘に言伝したそうです。そして上阪した時に先生に来て貰ったそうです。勿論資料として山本作兵衛の炭鉱絵物語集や炭鉱の坑内、坑外の写真を持っているだけ、持って行ったそうです。先ず「先生、私の今住んでいる家は、炭鉱時代に住んでいた社宅を、そのまま格安で払下げて貰ったんですが(山野炭鉱閉山時、全従業員に払下げ)どの位の広さがあると思われますか」と質問したそうです。返事は無かったけれども、マイナスのイメージしかない先生は、テレビで放映されていた倒れかゝった廃屋の長屋を思い浮かべていたのではないか、と思ったそうです。そこで「敷地が百坪で、家は四〇坪ですよ」と言うと先生はビックリされたそうです。「土地の百坪はそのまゝですが、家は新会社になった時に建て替えましたが、払下げ当時の社宅は三一・五坪でした。近所は皆その位いの大きさです。勿論私達の社宅は職員社宅で広いんですが、鉱員社宅でも土地は二〇内至三〇坪以上ありますよ。私は三井鉱山の山野鉱業所に閉山まで勤めていましたが、三井鉱山は北海道に三つ、九州に三つの大きな炭鉱を持っていました。九州の三山では山野が一番小さくて三井田川炭鉱が山野の倍、三井三池炭鉱が田川の倍、つまり三池は山野の四倍以上の規模の炭鉱で、日本で一番大きな炭鉱です。大牟田市は三井三池の城下町だったのは先生も御存知でしょう。山野が九州の三井系で一番小さいと言っても、筑豊炭田では有数の炭鉱で、最盛期には八〇〇〇人の従業員がいました。「イロハニホヘト」のお婆ちゃんではありませんが、戦前から日本の義務教育の普及率は百パーセント近くで世界のトップクラスであったのは先生も御存知の通りです。稲築町にも同和の人がいますが、略全員、義務教育は受けている筈です。特に生活のし易い炭鉱地帯で、子供を学校に行かせないとは余程親がどうかしているのでしょう。これは同和とか差別の問題ではありません。昔から炭鉱に行けば食える、というので全国各地から種々雑多の人が炭鉱に来ていましたので、炭鉱長屋の生活は実に解放的で、隣近所は親類付き合い、差別感等は殆んどありませんでした。部落出身者でも優秀な人はドシヽヽ職員に昇格していました。(戦前の三井の炭鉱では職員のことを役人さんと言っておりました。)私達は係員会議の後の打上げ宴会の時には、部落出身の係員ともお互に盃の献酬もしていました。それ位、炭鉱には差別感はありませんでした。
又、私の住んでいる地域は、枝坂の職員社宅と言われて、稲築町でも教育程度、生活程度は一ランク上のエリート集団の住宅地でした。山野炭鉱には旧制帝国大学出身者が、技術系、事務系に夫々一人は必ず入って来ましたし、それに私大出身者、旧制高等専門学校卒、そして実業学校出身者がズラリ居た訳ですから………(現在の大学進学率よりも、戦前の旧制中等学校進学率の方が遥かに少なかった。)
終戦前後には学校の先生を辞めて、炭鉱に再就職された方が何人もいた程です。先生方はマイナス情報ばかりしか知らないので、本当の炭鉱の実態を御存知無いのは当然ですが、有名な山本作兵衛さんの炭鉱絵は、明治・大正・昭和初期の小炭鉱の絵で、私達が三井山野に入社して閉山になるまでの炭鉱とは雲泥の差がありますよ(ここで三井山野炭鉱の第一立坑櫓、立坑庭園、坑内電車、坑道の施枠状況、採炭現場の水圧鉄柱、コンベヤー等の写真をお見せする)。坑内の状況は写真の通りですが、昭和二十年代後半の大学生の入社希望ランキングの何年かは、三井鉱山が第一位でした。今からは想像も出来ないですね。三井山野陸上部は、日本製鉄と肩を並べる名門陸上部でした。特にマラソンでは古賀新三さんという当時ダントツのランナーがいましたし、オリンピックのマラソンランナーも出た位です。文化活動も活発で毎月二回新聞が発行され全家庭に配られましたし、各趣味の会も盛んでした。全社的には毎年、山神社祭り、全山対抗大運動会、盆踊り大会、花火大会等があり、会社直営の映画館も有りました。生活面で一番良かったのは、社宅の家賃、水道料、光熱費は全て無料だったことです。炭鉱の生活がし易かったのは当然ですね。大炭鉱は軍隊で言えば師団又は軍団と一緒で、全て自分で賄う組織を持っていました。例えば、三井山野病院は、内科、外科、耳鼻咽喉科、眼科、歯科、小児科の診料科目を持つ総合病院でした。
炭鉱と言えば「イロハニホヘト」ではありませんが、一般に比べて教育程度の低い集団と思っているでしょうが、先にもお話しました様に程度の高い人達が多く、技術系の職員になる為には、先ず国家試験に合格しなくてはなりません。特に鉱長、保安監督員になるには、甲種上級保安技術職員試験に合格する必要があります。その試験課目は⑴鉱山保安法規 ⑵坑内保安 ⑶坑外保安 ⑷電気保安 ⑸機械保安 ⑹防爆保安 ⑺鉱害保安、の七課目があり、これを受験後三年以内に全課目を取れば良い事になっていました。炭鉱が閉山して建設会社を設立しましたので私は引き続いてその会社に入りましたが、必要な国家試験を逐次取って参りました。例えば一級建築士、一級土木施工管理技士、第二種下水道技術者等ですが、その中で最も難しかったのが甲種上級保安技術職員試験でした。合格率は五パーセント内外でしたから。それ位炭鉱という所は、世間に流布されている様な程度の低い者で出来る仕事ではなかったんですよ………等々お話をすると、先生はビックリして「認識を改めました。矢張り経験された、実情に精わしい方に話を聞かなければ駄目ですね」と頻りに言っていた、とT君は話してくれたが、彼も日頃の胸のつかえが大分降りたことだろう、と思いました。
私にもその様な経験がある。長男が鹿児島大学だつたので、鹿児島の娘さんと結婚したが、父親が国鉄の職員で官舎住いであった。話が決ったので夫婦で鹿児島の官舎まで御挨拶に行ったが、先ずその狭さにビックリした、炭鉱の職員社宅にこんな狭い家はない。次に嫁の両親いわく「お父さんのお仕事が炭鉱だというので失礼でしたが身元調査をさせて頂きました、新聞やテレビで盛んに報道するものですから少し心配になりまして」との事、後日、嫁と両親三人で返礼に来宅されたが、「これが炭鉱の社宅ですか、広いですね」と先ずビックリし、山野炭鉱の第一、第二立坑を見学して貰ったが、自分達の持っていた炭鉱のイメージと全然違うので「炭鉱とはこんな所ですか」と感嘆久しくしていたのが強く印象に残っている。
以上、炭鉱に対する世間一般が持っている見方と……これは一方に偏したテレビ、マスコミの報道そのものであるが……現実に炭鉱生活をしてきた者との百八十度違う感じ方の例であるが、げにマスコミの影響力の強さには今更ながら恐しいものを感じている。
『異郷の炭鉱 三井山野鉱の強制労働の記録』
「イロハニホヘト」で述べたように、炭鉱閉山の相ついだ頃の、マスコミ、テレビの暗い面ばかり強調した報道は、炭鉱の実態とは違う誤まったマイナスイメージを一般に植えつけてしまった。更に上野英信氏、吉田清治氏、林えいだい氏達の出版された、炭鉱に関する写真集や、強制連行、強制労働のレポートは、これに追い打ちをかけるものであった。我々炭鉱で実際働いてきた者は「違う!!そんなことはない!!」と悲憤慷慨しながらも、それを正すべき手段もないまゝ今日に到ったが、今年(平成十二年)になって(『異郷の炭鉱 三井山野鉱の強制労働の記録』以下、『異郷の炭鉱』と略記する。)という本が出版された。編者は武富登巳男・林えいだいとあり、その帯には「初公開!収容所設計図が語る戦時下の炭鉱」として、説明文に
「中国、朝鮮半島における国家ぐるみの労働者狩り、炭鉱での過酷な強制労働、虐待、逃亡、虐殺そして敗戦……。坑内係、特高、捕虜らの生々しい証言、手記、さらに焼却処分されたはずの三井山野鉱の収容所設計図によって、戦時下の炭鉱の実態を明かす」
とセンセーショナルな文字が踊っている。「三井山野鉱強制労働の記録」となっているので、元三井山野鉱に勤務していた者として大変興味を感じ、早速購入して一気呵成に読了した。その内容は、戦時中の朝鮮人、華工、捕虜の、いわゆる強制連行・強制労働の実態を、当時の関係者を尋ねて話を聞き、それを林えいだい氏が文章化したものが中心である。
証言十一篇(林えいだい氏の聞き書き)、手記三篇、資料五篇、設計図(半島人合宿、華工、捕虜収容所)そして林氏の特徴である写真多数である。手記の一篇は、三井山野鉱で最初の半島人切羽を担当された月足国夫氏が九州鉱山学会誌に寄せられた論文であり、これは我々採鉱技術者から見ても正しいと思われるものである。他の二篇は英国人捕虜の本を翻訳者の了解を得て抄約したものであるが、これは誤聞、伝聞の非常に多い本である。のちほど誤聞、伝聞の個所は指摘する。
この「異郷の炭鉱」を一読して直ぐに感じたことは、
⑴この編者は本当に日本人だろうか。
⑵このような一部のマイナス面ばかりを強調して、炭鉱の明るい面は全て省略したレポートで、編者が言うように筑豊の若い世代が、郷土に誇りを持てるだろうか。
⑶証言、いわゆる聞き書きは、林えいだい氏の持っている考え方に基づいて取捨選択して文章化している。過去に出版された強制連行、強制労働と文脈は同じである。いわゆる偏向している。
⑷炭鉱人の大多数が持っている「炭鉱時代は良かった」……林氏自身も「あとがき」に書いている……という気持とは全く正反対の、曲げられた事例のみが取り上げられている。
⑸全然正反対の証言が同じ本の中にあるが、編者は確かめたのか。推敲したのか。
⑹かつて三井山野鉱勤務者であり、炭鉱に誇りを持っている者としては、この様な図書が、真実の炭鉱として世間に、いや後世に語り継がれることには倒底我慢ができない。なんとかしなければ、と痛切に思った次第である。
稲築町は炭鉱で栄えた町である。主要な炭鉱のあった市町では、石炭資料館を建設している。県下でも大牟田市、田川市、直方市、宮田町には夫々特色のあるものが出来ている。稲築町でも或る程度の石炭資料は集めており、遅ればせながら、それを充実して石炭資料館を造り、「稲築町は石炭で栄えた町なんだぞ」と、孫子の代に伝承しようと計画したが、如何せん、バブルの崩壊で緊縮財政となり、資料館の建設は断念せざるを得なくなった。しかし石炭産業資料は散逸しない中に、できるだけ多く集めて後世に残すようにしようと、現在「石炭産業資料調査研究会」を持っている。早速、研究会関係者にこの「異郷の炭鉱」を読んでもらったところ、
「稲築町の中心企業であった三井山野炭鉱が、こんな偏向した図書で、戦時中の炭鉱とは、特に三井山野炭鉱ではこんな酷いことをしていたのかと、それが間違ったことであっても一旦出版されると、知らない人にはそれが真実になる。稲築町や三井山野炭鉱の名誉の為にも、「真実の炭鉱の実態」を残すべきだ、石炭産業資料調査研究会が主になって、『異郷の炭鉱』の中心となっている戦争中の半島人、華工、捕虜の「過酷な強制労働、虐待、逃走、虐殺」の事実があったのか、又、無かったのか、これを究明しよう、特に編者の武富登巳男、林えいだいの両氏は、炭鉱の経験もなく、坑内労働の実態も、戦時中の半島人、華工、捕虜の実態も知らない筈である。又、林えいだい氏の文章には坑内経験者には直ぐ判る、間違った記述が多い。経験者が正しい事を最も良く知り、その話が一番強い筈である。戦時中の半島人、華工、捕虜を使った経験者を出来るだけ沢山集めよう。個人々々では残念なことに物を言う場所がない、研究会として、当時はどうであったか、真実はどうであったか、という座談会を是非持つ必要がある」
という結論に達し、早速戦時中の半島人、華工、捕虜の使役経験者探しにかかった。しかし残念な事に三井山野炭鉱が閉山して二十七年が経っている、多くの経験者は東京や京阪神方面に再就職している。おまけに、戦時中となると、終戦の年に二十才の人も既に七十五才である。存命で元気な方も少くなっている。漸やく六名の方にお集り戴き、座談会を持つことが出来た。次項にその座談会の内容を記述する。これはテープから起したもので、座談会の内容そのままであり、林氏のような聞き書ではないことを附言しておく。
二、座談会「戦時中の三井山野における外国人労働者」
平成十二年三月二十四日開催
[座談会録・録音テープは未発掘である。――三輪註]
三、座談会を終って
「戦時中の三井山野における外国人労働者」の元炭鉱マン達の座談会をどのように読まれただろうか。『異郷の炭鉱』の記述とは、まるで正反対であることにも気付かれた筈である。
座談会の中で司会をされた佐井さんは、三年間のシベリヤ抑留経験者であり、戦時中の三井山野炭鉱における半島人、華工、捕虜の使役実態を、この座談会で初めて知られ「居室にしたって、設備にしたって、捕虜達は私等シベリヤ抑留者に比べるとまるで極楽じゃないですか……」と言われている。
『異郷の炭鉱』では、朝鮮の人は強制連行され、過酷な労働を強いられ、合宿はさながら強制収容所みたいに記述されているが、座談会では、そのようなことは全く感じられない。又、その行動も自由であった事が明確に示されている。ここで世界の何人も反論出来ない事実を述べる。現在、主要国の大都会で女性が夜中に安心して独り歩き出来る都市が日本以外にあるだろうか。しかもそれは戦後の平和な現在の日本に限らない。戦争中も、戦前も、江戸時代さえそうであった。日本人の遵法精神と規律の正しさは国民性なのである。その平和で安全な日本でも、殺人や犯罪は皆無ではない。ただ、その殺人や犯罪のみを一方的に、しかも針小棒大に報道し、書き続ければどうなるだろうか。南京大虐殺、強制連行、従軍慰安婦問題がその通りである。何も知らない人達は日本は世界で一番残虐で危険な国だと思い込むのは必然であろう。炭鉱の実態も全くその通りである。
「百人のうち、一人だけが文句を言っているという場合、その文句を言っている人間が、あたかも百人の代表であるかのように書くという方法がある。一パーセントの人間が文句を言っても、文句を言った人間の言い分だけを集めれば、ひどいことをしたということになる。しかし残りの九九パーセントの人達はそれで恩恵を受けているのが事実である。そういうものの見方をしなければ歴史上の事実は公平に評価は出来ない」というものの見方、考え方を読んで、全くその通りだ、と私の処世訓にしているが、現実に自治会等でも、反対する人間が一人か二人は必ず存在するものである。然し大多数の意見で物事は進行してゆく、これが民主主義であり、人間社会ではないだろうか。『異郷の炭鉱』を読んで直ぐ思い浮かんだのがこの論理であった。
又、同時に「この編者は本当に日本人だろうか」と思ったのは『論語』の中に、羊を盗んだ父親の罪を正直に役人に訴えた息子について、どう思うかと問われた孔子が「父は子のためにその罪を隠し、子は父のためにその罪を隠すことが正直なことだ」と言った、という有名な話があるのを直ぐに思い出したからである。これが人間の情ではないか。日本人の作家が、日本人の一パーセントの悪を、百パーセントみたいに何故書きたてるのだろうか。九九パーセントの炭鉱人は「炭鉱時代は良かった」と述懐しているではないか。この元炭鉱マン達の座談会でも、その思いに満ち溢れているではないか。これが真実なのである。
表題の副へ書きに「嘘や捏造、誤聞、伝聞を排す」と書いているが、座談会でもその指摘がなされている。座談会はその性質上、詳細に話すことは出来ないので、以下にその点について少し詳述したい。
『異郷の炭鉱』は聞き書の証言なるものが、主題である。編者の表現力、文章の巧みさには感心するが、これは編者の偏向した意図の元に、証言者の話を、ある一定の方向に取捨選択して纒められたものである。残念なことに編者には炭鉱、特に坑内での経験がないこと、その為か、嘘や捏造が多く、しかも相反することが平気で書かれていることである。以下に主な項目のみについて、その矛盾点を指摘しておく。
強制連行、強制労働について
我々は戦時中、半島人、華工、捕虜のいわゆる外国人労働者と一緒に働いてきた経験がある。しかし一九七〇年代後半から出始めた強制連行に関する出版物は、目に余る歪曲、捏造が多過ぎる。更に中学校社会科教科書にまで「朝鮮人や中国人を強制的に連行し、過酷な労働に従事させた。又女性も従軍慰安婦として強制的に戦場に送り出された云々」と記述され、コラムのような欄を設けて強制連行についての具体的な話を載せている。
例えば、教育出版には「朝鮮・中国から強制連行された人々」というタイトルで「筑豊(福岡県)の炭鉱の金さん」の例を紹介している。
金大植さんは、一九四三年(・・・・・)二月(・・)、(・)家(・)で(・)寝て(・・)いる(・・)ところ(・・・)を警察官と役場の職員に徴用(・・)令状(・・)を(・)つきつけられ(・・・・・・)、集結地まで手錠をかけられたまま、一二五名の朝鮮人同胞とともに日本に連行されてきた。日本へ送られる途中の監視は厳しく、便所へ行く時にも七人の監視係の目が光っていた。一行が福岡県の田川後藤寺駅に着くと、彼らの逃亡(・・)を(・)防ぐ(・・)ため(・・)に(・)、数百人(・・・)の(・)人々(・・)が(・)待ち受けて(・・・・・)いた(・・)(後略)[傍点は跡部による。以下同じ。――三輪註]
東京書籍は「朝鮮人強制連行」と題して次の様に書いている。
朝鮮人の強制連行は一九三九(昭和十四)年から始まりました。最初は「募集」という形式でしたが、それはけっして自由意志によるものではありませんでした。一九四二年からは朝鮮総督府による「官斡旋」となりました。日本の公的機関が直接関与するようになったのです。総督府の割り当てに応じるために、警察官や役人が土足(・・)で(・)家(・)に(・)上り(・・)、寝て(・・)いる(・・)男(・)を(・)家(・)から(・・)連れ出す(・・・・)こと(・・)も(・)ありました(・・・・・)。抵抗(・・)する(・・)者(・)は(・)木刀(・・)で(・)なぐりつけ(・・・・・)、泣き(・・)さけびながら(・・・・・)トラック(・・・・)に(・)追いすがる(・・・・・)妻子(・・)を(・)上(・)から(・・)けりつけた(・・・・・)、ともいわれます。(後略)
この様に強制連行については一様に「寝ているところ」「木刀でなぐりつける」「トラック」「追いすがる妻子を上からけりつけた」と、書かれている。これが本当に、戦前の修身教育を受けた、世界でも最も規律正しいと自負していた日本人の所業だろうかと、私にはどうしても納得がいかなかった。
私の叔父が日鉄鉱業に勤務していて、戦時中、朝鮮に募集に行っていたのを知っていたので、強制連行の有無を聞くと「強制連行とかいうことは絶対にない。終戦になって朝鮮に送還する時にも、苦労して便宜を計ったので大変喜ばれて、朝鮮に帰っても「有難う、大変お世話になりました」という手紙が何人からも来た位だ」ということで、私自身は「又、反日左翼人が煽っているな!」と思った次第である。
徴用令は内地では一九三九(昭和十四)年に公布されているが、朝鮮に徴用令が施工(ママ)されたのは一九四四(昭和十九)年であり、金さんの一九四三(・・・・)(昭和(・・)十八(・・))年(・)二月(・・)に(・)徴用(・・)令状(・・)が(・)ある(・・)筈(・)が(・)ない(・・)。完全な捏造である。又、田川後藤寺駅に着いた時、彼等の逃亡を防ぐため数百人の人々が待ち受けていた、とあるが、これも考えられないことである。逆に歓迎しに来ていたのではないか。座談会にも出ているが、山野新聞には「鴨生駅に迎へに行き、鴨生クラブで歓迎行事を行った」と出ている。本当にその様な惨酷な強制連行をしたのならば、彼等を収容する合宿所は、捕虜収容所以上に厳重な警戒がなされる筈であるが、現実の半島人合宿は、内地人の独身者合宿と殆んど変らない設備であり、まして座談会にも出ていた様に、自由行動が取れる筈がない。我々も一緒に働いて、朝鮮人が無理矢理、強制連行されて来た様子は全然感じなかった。
逆に「朝鮮人徴用工の手記」(河合出版)という本に出ている鄭忠海さんの手記には次のように書いてある。
一九四四(昭和十九)年の十一月末に徴用令状を受け取った鄭忠海さんは「……後を振り返りながら別れの言葉もそこそこに集合場所である永登浦区庁前の広場に向った。広場は出発する人、見送る人で一杯だった。………徴用者の点呼が終ると、一同は隊伍を組んで商工会議所の前に集まり、各地から動員されてきた人とともに壮行会が催された」(後略)
出発する人と見送る人で一杯だったと、それに壮行会もやっている。この手記からは、徴用された人は、歩いている時捕って無理矢理トラックに積込まれたとか、寝ているところを、とか、暴力的に拉致されたとは思われない。当時日本の施政権下にあって、日本の法律が適用されていたその地域で、合法的に、しかも壮行会まで開いて貰って、日本に渡って来た人達を、強制連行というならば、日本国内の徴用工も女子挺身隊員も全て強制連行と言わなくてはならない。
私が不思議でならないのは、日本人の中に嘘の証言をしてまでデッチ上げをしようとする者がいることだ。相手に阿ねって、嘘を言ってまで証言することが、相手に対する謝罪になると思い、それで自分は免罪になると思っているが、私は逆に侮辱していることになると思っている。従軍慰安婦問題でもそうであるが、寝ているところを土足で踏み込まれ、手錠をかけられてトラックに積み込まれた。抵抗するものは木刀でなぐりつけ、泣き叫びながらトラックに追いすがる妻子を上からけりつけた。この様な強制連行の実態があったとすれば、誇り高き朝鮮民族が黙っている筈がない、必ず暴動が起っている筈である。それなのに暴動は起っていない。それが事実ならば、終戦の時、朝鮮にいた日本人は全員無事引き揚げているが何故だろうか?。朝鮮民族は踏んだり、けったり、その様な侮辱を受けても無抵抗の情ない民族だったのか?そうなるではないか。私は呉善花の「スカートの風」三部作、金文学、金明学共著の「韓国民に告ぐ」等を読んで、矢張り朝鮮民族は日本人にはない素晴しいものを持っていると思っているが、その民族が、終戦後の日本が無力になった時期でさえ、日本人に対して余り反抗しなかったという事実は、当時、現在言われているような強制連行はなかった事を示しているのではないか。
反日左翼文化人あるいは反戦平和を叫ぶ人達は、社会主義国家は労働者の天国であると言って批判がましいことは一言も言わなかった。今では笑話になっているが、私が昭和四十年の山野炭鉱ガス爆発で被災し、入院している時、共産党員になっていた友人が見舞に来て曰く、「資本主義社会では儲けることばかり考へて保安の手抜きをするからこんなことになる。中国では炭鉱の爆発事故なんか絶対にあり得ない、蝿なんて一匹もいない」と、そこで私は「資本主義社会の経営者も馬鹿じゃないぞ。保安の手抜きをして一旦このような大事故を起せば会社は潰れるじゃないか、それ位は判っているよ。この様な事故というものは人間の盲点をついて起るものだ、保安には萬全を盡した積りでも必ず盲点はある。人間は神様ではない、必ず手ぬかりはあるもんだ。然しそれを一方的に保安軽視とあんた達は言うが、中国でも必ず落磐事故はあるし、ガス爆発も起る筈だ。又、蝿が一匹もいないという事も絶対に信じられない」と反撥しておいたが、現在ではどうであろうか。ソ連の崩壊と共に、社会主義国家の実態が明らかになって来た。ソ連は戦争が終っているのに、百万人の日本人をシベリヤに強制連行抑留し、四〇万の死者が出たというのに、共産中国では、あの大躍進や文化大革命の時には夫々二千万人が死んだと言うのに、左翼かぶれの人達は未だにそのことについては何も言わない。中国が解放政策をとって日本人の旅行者も随分増えて実態が見えて来たが、それでも蝿は一匹もいないと言い張るのだろうか。ごく最近、中国の炭鉱でガス爆発事故があり、多数の犠牲者が出ているが、これはどうしたことなんだろうか。釈明して貰いたいものだ。
強制労働についても、マスコミや、この手の出版物には捏造された誇張された嘘が、まことしやかに報道されている。どうしてこのような論理になるのか、炭鉱の一技術者としては理解に苦しむのである。
次に強制労働について、その虚構を若干述べる
(一) 死との闘い(『写真万葉録・筑豊2 大いなる火(上)』上野 英信、趙 根在)
「日本敗戦の翌年、〈筑豊〉地区における労働者一人当り月平均出炭能率は五・二屯に過ぎなかったが、一九五〇(昭和二五)年に八・八屯、一九六一(昭和三六)年には一八・六屯、一九六五(昭和四〇)年には三三・二屯へと急上昇している。いかに恐るべき労働強化によって戦後復興の原動力が確保されたか、あきらかであろう。」(P35)
(反論)
能率の上昇は全て労働強化による、と吹き込もうとしている。人間の労働力の差というものはたいしたものではない。能率上昇の主因は、合理化、機械化によるものが大半である。能率上昇が労働強化によるものとすれば、日本やアメリカの様に生産性トップの国の労働者は、給与水準が百分の一から良くても十分の一といわれる後進国の労働者の百倍から十倍の労働強化を強いられているのだろうか。
(二) 危険な作業は朝鮮人(強制労働の殆んどのレポートにある)
危険で、骨折る作業、条件の悪い所には朝鮮人を繰込み、内地人は安全で楽な仕事ばかりをした。従って朝鮮人の死傷者が増加した。
(反論)
新聞記者が喜ぶような、そして炭鉱のマイナスイメージを強調したい人達には、直ぐに飛びつく事例であるが、これをそのまま信じる人は坑内の実情を知らない人達である。石炭の採掘現場というのは、高さ一・五米乃至二次・〇米位の石炭層を、長さ五〇乃至百米位で、全体を一日に一米とか二米とか掘ってゆくものである。例えば、高さ二・〇米、切羽長百米、進度二・〇米とすれば、一日出炭量は四百立方米、石炭の比重一・三とすれば五二〇屯の出炭となる。これを一番方の採炭とすれば、二番方は充填方(コンベヤーの移設や、発破産炭、硬巻作業等)となり、これの繰返しである。従って一日進度二・〇米の予定が、一部断層や天井の悪い所では、普通の能力しかない人だと一・五米位しか掘れない。それではコンベヤーの移設が出来ない。コンベヤーの移設が出来ないと、明日からの出炭に差しつかえるので、その様な箇所には最も技能の優秀な人を繰り込まざるを得ない。危険で条件の悪いところには内地人の技能の優秀な人を繰込まないと、一様な二・〇米の進度は確保出来ない。三井山野の朝鮮人は、早く来た人でも四年から五年の経験しかない訳である。条件の悪いところ、危険な個所には経験の豊かな、技能の優秀な人でなければ対応出来ない。従って「危険な作業は朝鮮人」というレポートは全くの嘘である。
(三)炭鉱では死人が多く毎日の様に葬式があった。(『清算されない昭和 朝鮮人強制連行の記録』林えいだい写真・文、高崎宗司解説)
炭鉱の坑内作業は、地下の作業であり、自然が相手であるから、危険な作業であることは事実である。坑内作業は危険であるのは承知の上で仕事をしたのである。その理由は、坑内勤務は待遇が良かったからである。然し、「毎日の様に葬式があった」という記述は納得出来ない。『写真万葉録・筑豊1 人間の山』(P23)に、一九二七年から三一年までの五年間で、日本全国の炭鉱坑内での死亡者、三八五二名とある。大正末から昭和の初期であり、坑内事故の多かった頃の実績であるが、それでも年平均七七〇名の死亡者である。それも全国である。全国で何百と有った炭坑で、毎日の様に死人が出ていたならば、七七〇名では済まない、何万名にもなるだろう。現在自殺者は年間三万人を超し、自動車事故による死亡者は一万人前後である。三井山野炭鉱では、坑内事故による死亡者が出ると「今年は死人が出たばい、又、保安が厳しくなるばい」と言われていた位、何年かに一人殉職者が出る位であった。(ガス爆発事故は除く)なのに「毎日葬式!……」という聞き書による表現は、炭鉱労働者の味方であるかの如くではあるが、朝鮮人の強制連行と同じように、実は炭鉱労働者を侮蔑したものである。
(四)大出し日は、翌朝まで働かされた云々(『異郷の炭鉱』)
(二)の危険な作業は朝鮮人云々で述べたように、採炭現場は、採炭と充填の二交代制であり、戦争中の大出し日は確かに朝七時に入坑して夜の八時に昇坑する事はあったが、翌朝まで働くことはありえない事である、充填作業が出来なければ次の採炭は出来ないではないか。又、坑内安全灯は十二時間以上の使用は暗くなって駄目である。大出し日には翌朝まで働かされた云々はあり得ないことであり、全くの嘘である。
『異郷の炭鉱』には、おかしな記述が随所にあって、まるで正反対の話が堂々と掲載されている。編者は経験者から話を聞いて、文章化されたのであろうが、この矛盾には気がつかれなかったのだろうか。
強制連行、強制労働については前述したので、朝鮮人逃走について、その矛盾点を明らかにして行きたい。
1のイ(序 武富登巳男 P20)「それにしても半数逃走とはひどい。半数は八万六一〇〇人、そのうち一割は発見され、連れ戻されたが、九割の八万五二三九名は消息不明で、まったく解明されていない。」
1の口(同前 西田 彰さんの話 P21)「朝鮮人逃亡者は何とか逃げのびた者もいるが、土地勘がないし大方はすぐ捕った。八木山峠などには警察、消防団などが非常線を張っていたし、憲兵もきびしかった。」
(反論)西田さんの話では、逃亡者は大方捕えた、とあるが、逃走実績では、発見されたのは一割である。又、戦時中に警察、消防団、憲兵が、朝鮮人逃走防止の為に非常線を張るような余裕は全く無い筈であり、武富さんの序では九割は消息不明で、まったく解明されていない、と記述し、さも殺されたかの様な印象を与えるが、現実には炭鉱以外の各地同胞のいる所、或は小炭鉱等に逃げたことは明らかではないか。ただその詳細が判らないだけの話である。
2のイ(編集にあたって 林えいだい P22―23)「第一にいえることは、国民徴用令を適用して、国家ぐるみで強制的に朝鮮人狩りを行ったことである………日本到着までは一人の逃走者もなかったという。」
2の口(同前 P24)「連行途中の列車から飛び降りたり、釜山での船待ちの旅館から逃走して、炭鉱に到着したら半数しかいなかったところもあった。」
(反論)どちらの話が本当なのかまるで判らない。しかもこれは「編集にあたって」の林えいだい氏の文章のP22―P24の記述である。支離滅裂である。このような正反対の記述が随所にあるのである。
3のイ(同前 P24)「軍需省からの石炭増産の命令は気狂いじみてきて、炭鉱には〝大出し日〟という制度が設けられた。
週末の土曜日になると翌朝まで採炭させた。日曜日の朝に寮に帰ると、もう夕方には出勤しなければならない。それが続くと、一ヵ月間に一度も休めなかったのである。
一ヵ月に四度の〝大出し日〟があると、体力に限界がくる。「殺されてもいいから炭鉱から逃走したい」
彼等は死を覚悟して逃走の道を選んだ。」[傍点は跡部による。以下同じ。――三輪註]
3の口(証言 特高 元飯塚警察署特高主任 柿山重春 P54―55)
「当時、労務管理で一番困ったのは朝鮮人の寮からの逃走で、これだけはどこの炭鉱も共通の悩みだった。
最初の募集の頃と、後期の徴用の時代となると、強制連行の内容がまったく違ってきたからね。一九四〇年、四一年までは、内地へ行きさえすればどうにかなるという野心家がおって、募集を利用して日本にやってきてから、すぐ逃走するケースが多かった。それは朝鮮では生活できないからという、良心的なものだったからね。
…………寮の周囲に板塀があったところで、人間がいったん逃げようと思えば、あれくらいの障害なんか平気なものでね。刑務所とか監獄と違ってわけはない。
筑豊の炭鉱にくると(そこの朝鮮人寮とか周囲のありらん部落には、親戚とか同郷の者が必ずおるからね。外の炭鉱とか工事現場なんか、どこが金になるとかならんとか詳しいからね。いろんな誘いもかかってくる。あるいは大阪あたりの親戚に行こうとか、すぐ打合せて逃走するから油断ならんやった。」
3のハ(証言 暴動鎮圧 元田川警察署特高主任 満生重太郎 P60―61)「最初、大手の炭鉱に強制連行された朝鮮人坑夫は、そのうち小炭鉱へ逃走した。
炭鉱のあるところには、必ず坑夫を斡旋する専門の手配師がいて、炭鉱が専属で雇っている。嘘八百並べ立てて、町に遊びに出た朝鮮人に誘いをかける。飯をいっぱい食べさせるとか、賃金を倍も出すからとか、一週間に二日の休みがあるとか、彼等が飛びつきそうなことを言うので、それを信じてころっと騙されてしまう。
だから小さな炭鉱では、朝鮮募集の労なくして労働力を確保した。
………強制連行される前から大阪あたりに行こうと決め、炭鉱はワンステップと考えていた。」
(反論)朝鮮人逃走の原因は、林えいだい氏等によれば、食べるものも食べさせず、こき使われ、肉体的にも限界が来て、殺されてもいいからと覚悟して逃走したようになっている。ところが当時の特高主任のお二方の証言は、ともにそうではない事を話されている。ここで注意しておきたいのは、特高主任のお二方が、強制連行という言葉を使っておられる点である。当時、強制連行という言葉はなかったし、この証言はいわゆるお二方の話を聞いて、林えいだい氏が文章化したものであるということである。若しお二方が強制連行という言葉を使われたとすれば、従軍慰安婦と同様で、その様なものはなかったのにこの二十年来、マスコミが盛んに言うので、我々もつい従軍慰安婦と口には出すが、内心ではただ慰安婦と思っている。朝鮮人募集も、いつの間にか強制連行になってしまったが、お二方も内心では募集と思われている筈である。なお、林えいだい氏は朝鮮人強制連行の専門家と言われているそうである。又、お二人の証言の中からも、朝鮮人が自由に行動していたことが読み取れる。本当にこのような強制連行、強制労働があったのならば半島人合宿は必然的に強制収容所となり、このような自由行動はとれない筈である。しかし前述したように、現実に当時を経験してきた我々から見ても、一緒に働いてみて、その様なひどい強制連行で来た者達という感じは全く無かったし、その様な強制労働の実態も無かったことを、座談会の元炭鉱マン達も語っている。
四、「たいしたピクニックじゃなかった」の嘘や誤聞、伝聞について。
林えいだい氏は「編集にあたって」の中で「捕虜の炭鉱労働の詳細についてはイギリス人捕虜のバクスター氏が記録しているので省くことにする」と書いており、ジョン・バクスター氏の『たいしたピクニックじゃなかった』(赤間正久訳)から抄約したものを、手記として掲載しているが、この捕虜記は非常に誤聞、伝聞の多い本である。極端に言えば嘘の多い本である。彼が一九四一年に徴兵され、一九四二年にジャワで日本軍の捕虜となり、終戦まで稲築町の三井山野炭鉱の工作課電気修理工場で戦時捕虜として働かされた人であり、終戦後、長崎、カナダを経て、母国イギリスに帰るまでの捕虜体験を『たいしたピクニックじゃなかった』として発表されたものである。
訳者の赤間正久氏は、稲築町文化連合の会長をされており、バクスター氏の三井山野炭鉱の捕虜時代のことが書かれている、というので興味深く読ませて貰ったが、戦時中の当時を知っている者として、三井山野時代の記述が嘘や、誤聞、伝聞が多く、従って、三井山野炭鉱以外の、捕虜になって以降、故国に帰るまでの話が、どこまで信用して良いのか全くわからない。以下に原文を転記し、どこが嘘であり、誤聞、伝聞であるかを指摘してゆきたい。
キャンプへの途中駐在所を通っていった。その玄関口に一人の日本の若者が逆立ちをしていた。護衛兵は、彼は泥棒で、あれは罰を受けているのだと説明した。玄関前を通るものは誰でも、そこでゆらゆらしている不運な彼を蹴ったり、叩いたりするように要求された。このことからして我々は、この原始的な習慣に慣れ………P115
(日本の駐在所で、特に三井山野炭鉱の駐在所でこの様な刑罰が行われていたとは、見たことも聞いたこともない。逆にイギリスやジャワではこの様な刑罰があったのでは…………。全くの握造)
草も生えていなければ木一本見られなかった P115
(砂漠ではあるまいし、稲築町では、硬山以外にこんな所はない。捕虜体験記としての誇張である)
入坑の方法は話せば身の毛のよだつようで、ウインチマンがブレーキを緩めると十二台か十三台のトロッコが1/10勾配の真っ暗な中を恐ろしい勢いで突き進んでいった。際限なく長い時間にように思われたが多分半マイルぐらいだった。後の制動手(ブレーキ係)が車輪を遅らせるためブレーキをかけると、金属の痛ましいきしみ音がしてトロッコは地下の第一の場所に停止した。P120
(斜坑の人車のことを指していると思うが、人車は、人車自身のブレーキで止めるものではない。人車の通行は巻上機により運行、停止が行われる。最先端と、最後備に車掌が乗っており、それの信号により巻上機の運行、停止は行われる。坑内経験者ならば直ぐに判ることである。バクスター氏は工作課の電気修理場に配属されており、坑内の経験はない。従って、この話は誤聞、伝聞の類いである)
坑内はすっかり掘り尽されていた。炭層の薄い低質の石炭が残っているだけで、ほとんど岩ばかりであった。………中略………
戦時のもの不足からワイヤー大綱は鋼鉄線をより合せて作られており………P121
(炭層が堀り尽されていたのならば、三井山野炭鉱は、終戦と同時に閉山していなければならない。又、ワイヤーはもの不足から鋼鉄線をより合せて作られており………とあるが、ワイヤー大綱は、柔軟性と強度を保つため、細い鋼鉄線をより合せて作るものである。関門大橋や明石大橋の、あの大きなワイヤーも、全てその様にして作られている。もの不足からではない。バクスター氏の見解は技術者にあるまじきものである)
我々は東洋の教育水準はとても低いことは知っていたけれども我々は常に十まで数えることの出来る数少いものがいたかもしれないと考えなければならなかった。P123
(バクスター氏は四二年から四五年まで日本の捕虜として、日本人との接触があり、日本人の教育程度は知っている筈なのに、こんな表現をするのは東洋人蔑視の現われである。当時の日本人で十まで数えきらない者は一人もいない。普通教育の就学率は当時でもトップクラスであった。アメリカ兵等には掛算、割算の出来ない兵隊が大分いたとの事である)
ああ、我々のすべての努力も日本人監督者の努力も水泡に帰した。その夜我々は非常に激しい空爆に会い、その空爆中ときおり千ポンド爆弾が落下し正確な投下だったので二台のぴかぴかのエンジン車に的中し、二台とも鉄のスクラップに至らしめることになった。P130
(三井山野炭鉱が空爆を受けたことは無いし、フィリピンから持って来たというエンジン車の話も聞いたこともない。又、当時の爆撃機に夜中でも命中させる様な、湾岸戦争の時のようなあのハイテク機能があっただろうか。これは完全な捏造であり嘘である)
炭車を暴走させた話P134
(斜坑巻上機の運転手が十凾の実炭車を吊り下げたまゝ、巻上機を離れることはない。又、斜坑巻上機は三百内至五百馬力であり、素人が巻場に侵入して、簡単にブレーキを弛めることは出来ない。この話も誤聞、伝聞、捏造の類である)
イギリス空車のあの見慣れた国籍マークをつけて………連合軍機が去ってすぐ後近くの爆弾備蓄所からと思われる大爆発を聞いた。谷間を見下ろして我々は空中に何百フィートもゆっくり上がる大きなきのこ雲を見ることが出来た。我々が近くの爆発と思っていたのは実は長崎に落された原子爆弾だったのだ。P149
(稲築町の三井山野炭鉱から長崎の原爆が見える筈がないし、戦争末期の連合軍機は全て米軍機であった。これも完全に嘘話である)
バクスター氏の三井山野に於ける捕虜生活の記述を読んで、特に三井山野が爆撃されたとか、稲築町から長崎の原爆が見えたとか、全く嘘の話が多い。特にバクスター氏は、工作課の電気修理工場に配属されており、坑内経験は全く無い。坑内の話はすべて伝聞であり誤聞である。バクスター氏の、今から言えば貴重な捕虜体験記であり、良く見せようという心情は分かるけれども、余りに嘘や誤聞、伝聞が多い。従って捕虜になって解放されるまでの話も全ては信用出来ない。
しかし、これは当時の現場を知っている我々だから言えることであり、事実を知らない一般の人がこの本を読むと、書かれていることが真実であると思うであろう。「一犬虚に吠えて、万犬実を伝う」とはまさにこの事であろう。実に恐しいことである。
五、むすび
以上で『異境の炭鉱』の記述が、文章は巧みではあるが、如何に当時の炭鉱の暗部のみを摘出し、誇張したものであるかが理解されたことと思う。
最後に、半島人合宿と捕虜収容所について若干述べておきたい。
『異郷の炭鉱』の帯に「さらに焼却処分されたはずの三井山野鉱の収容所設計図によって戦時下の炭鉱の実態を明かす」と書かれており、新聞にも一時報道されたことがある。さながら昔の建設現場のタコ部屋を連想させる様な書き方であるが、いざその設計図の現物を一見してビックリした。その構造のシッカリしていること、一人当り居住面積の広いこと等、戦時中の合宿、収容所設備としてはこれ以上のものはないと思った。座談会の中でも述べているが「日本人の鉱員住宅よりも良いではないか」と思われるものである。これは編者の意志とは逆の効果を与える結果となったようだ。私は三井山野炭鉱で生れ、三井山野炭鉱で育った人間であるが、私の幼年期に住んでいた鉱員住宅は、六畳、四畳半の二部屋の長屋であり、そこに九人の親子が入っていた。一人当りにすれば畳一・一七枚で、半島人や華工、捕虜収容所の方が広いではないか。更に半島人合宿の設計図に「逃走防止用」として高さ七尺の板塀を設ける、と申請してあるのを発見して、鬼の首でも取った様に各所に書いているが、これは当時、戦争中であり、統制経済の中で、あらゆる資材は配給であった。従って合宿の周囲を囲う板塀の材料の配給を受けるため「逃走防止用」と理由づけしたに過ぎない。その証拠に、特高主任の証言は「あの程度の板塀は逃走防止用にはならない」と言っているし、現実に朝鮮人は自由に行動をしていたではないか。七尺の板塀が出来たから逃走が減ったかと言えば何も変ってはいない。あの板塀は飽くまでも境界用の板塀であり、逃走防止用ではない。ちなみに日本人独身者用合宿の周囲にも同じような境界板塀のあったことを編者達は知らなかったのであろうか。
「百年前を批判する時、現在の目で見てはならない。百年前の時点に立って、ものを見なければならない」と良く言われるが、現在でも東京や大阪の簡易宿泊所は、二段ベッドの畳一枚ではないか。一パーセントを百パーセントの如く誇張してはならないと泌々思う次第である。
平野準人さん(バクスターの指導員、稲築町枝坂に居住)の証言の中に「鴨生駅で降りてトラックに乗せられた捕虜が、収容所の方へ向って行った。
よく見ると彼らは、ギターやアコーデオンを弾いて、とてもにぎやかだった。
戦争捕虜というのに、まったくじめじめした雰囲気がなく、とても朗らかな一団だった。捕虜のくせにどうしたことかと驚いた」(『異境の炭鉱』、P118)
又、「食事が終ると、靴でリズムをとってタップダンスをしたり、スプーンを二本手に持つてカチカチ合わせ、歌を歌ったりして楽しんでいた。これでも戦争捕虜なのかと、あきれ返って私は見ていた」(同前、P120)と話されているし、捕虜も半島人もあの食糧の不足している時でも、三度々々食事はしていたし、毎日入浴もしていた。半島人にいたっては、独身の合宿居住者でも、自由に出歩くことが出来たし、妻帯者は、日本人と一緒の住宅で生活をし、風呂も一緒の風呂であった。
イギリス人のもう一人の捕虜、エディ・ホーキンズ氏の「第八俘虜収容所の実体」が抄訳され、手記として掲載されているが、彼は結論として「この収容所でなされた炭鉱の労働が、戦争捕虜として適切なものであったかどうかは、国際法の専門家にお任せするが、日本人はおそらく条件は日本人と同じだったと主張するだろう。
私はこれにはうなずけるところがあるのだが、とにかくこの申し立てを考慮する人は、戦争中の炭鉱の事情に詳しい人であってほしいと願うものである」(同前、P147)と言っている。
反面、シベリヤ抑留者は、戦争中の捕虜ではなく、戦争が終っているのに強制的に連行され、四十万とも言われる犠牲者を出しているが、その労働の実態は座談会にも一部紹介されている。いみじくも佐井さんが「居室にしたって、設備にしたって、捕虜達は、私達シベリヤ抑留者に比べると、まるで極楽じゃないですか。この本では捕虜達は畳一枚半だったと書いてあるが、私達は畳一枚に二・五人詰め込まれていたんですよ」と言う一連のお話に、真実は集約されているのではないか。ソ連に比較し、日本には、いわゆる強制連行・強制労働の実態はなかった。私達は胸を張って、そう言うべきであろう。
ソ連のシベリヤ抑留者の条件と、設計図に見る半島人、華工、捕虜達の一人畳一・五枚という、日本人と同等の設備、そして半島人の行動の自由、逃亡の本当の理由等から、編者はどのような真実を見ているのだろうか、教えていただきたいものだ。
しかも当時は、戦争の極限状態であり、日本民族の生死をかけて、総力を結集して、米国、英国、支那、オランダを相手に戦っていた時である。非常の時を、平和な平時の視線で批判してはならない。
戦争の極限状態の異常な時期の、一パーセントの暗部を暴き、それを強調して、何も知らない戦後世代が、郷土に誇りを持てるだろうか。私は編者が、この『異郷の炭鉱』の最後に、いみじくも言っている「昔の炭鉱は良かった」という、九九パーセントの炭鉱マン達の語る、明るくて、解放的で、差別のない、活気の溢れていた、炭鉱の真実の姿を、文章能力の優れた編者に、活写して戴きたいと願うものである。
(文責 佐井、跡部)